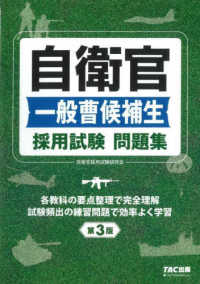出版社内容情報
世界無形文化遺産「和食」はどのようにかたちづくられたか。素材を活かし、旨みを引き立て、栄養バランスにすぐれた食文化が、いつどんな歴史のもとに生まれたかを探り、その成り立ちの意外な背景を描く。
内容説明
一般的には一汁三菜にイメージされる和食。世界無形文化遺産に登録された、素材を活かし、旨みを引き立て、栄養バランスにもすぐれる和食の文化は、いつどんな歴史のもとに生まれ、かたちづくられてきたのだろうか。それを古来の神饌料理、高度な調理技術が際立つ精進料理、味付けの粋を極めた本膳料理と懐石料理などから探り、出汁や調味料による旨みの文化という観点から、独自の発展を遂げた「日本の味」の全貌を描く。
目次
1 米と魚の文化―和食の源流
2 神へのおもてなし―和食の原型
3 外来の料理―和食と中国
4 旨みの食文化―和食の成立
5 旨みの創出―和食を支える工夫
6 楽しみとしての江戸の料理―和食の発達
7 新たな料理へ―和食の近代と現代
著者等紹介
原田信男[ハラダノブオ]
1949年生まれ。国士舘大学21世紀アジア学部教授。明治大学大学院博士後期課程退学、博士(史学)。ウィーン大学客員教授・国際日本文化研究センター客員教授・放送大学客員教授を歴任。専攻は日本文化論・日本生活文化史。『江戸の料理史』中公新書でサントリー学芸賞、『歴史のなかの米と肉』平凡社で小泉八雲賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
55
明治に西洋料理が入り「和食」が生まれた。その違いは天武天皇675年の肉食禁止令にある。明治4年明治天皇が肉食再開宣言を行う。肉でだしがとれないので北の昆布と南の鰹節で出汁をとった。海運が進んだ室町時代が日本料理の発展時期。元々神饌料理で素材と調味料を別にしていたが、大饗料理から禅の影響で精進料理となり、茶の湯から懐石料理へと変化した。江戸時代から天ぷら・寿司・蕎麦が拡がり、明治になり肉食が普及。戦後食糧難で米国から支援で給食にパンと乳製品が支給され、コメ離れに至る。元教授だけあり食の文化史がよくわかる。2019/05/22
佐島楓
29
稲作特有の文化からの食の発展、茶の湯と共に和菓子や懐石などが発明された室町期、一気に食文化が開花する江戸期と、読んでいて楽しかった。特に江戸時代の「起こし絵」というペーパークラフトのようなものは、文化的に余裕があった時代の発行物であったことがうかがえる。写真、図版なども豊富で、良い本だと思う。2014/07/25
nizimasu
5
和食って何と言われても実はわからなかったりするのですが、土地のものをありがたく頂く地産地消が当然だった時代の稲作文化から精進料理、そして茶の湯を経ての本膳料理と言う流れは日本の長い食文化が貴族から宗教者、商人発の食の文化が入ってくるあたりは、まるで大河ドラマでもみているかのよう。中でもだしの文化って、やっぱりどうもかなり特徴的に感じるのはこの本の強調する点なのかも。にしても日本の食文化の芳醇さが何とも微笑ましくなる内容です2014/10/07
niz001
3
薄いけどしっかりした内容の本やな。和食の歴史と文化がうまくまとめられててよくわかる。2014/07/02
kei
2
和食は世界遺産に指定されるなど注目されています。特異な和食が生まれるまでの過程は謎が多いですが、神に捧げた神撰食から始まり、味噌、醤油、出汁の誕生まで概説されています。地理的、宗教的要因(政治的?)で家畜を用いなかったことが、こんな特異な食事につながるとは。面白かった。2014/07/04
-
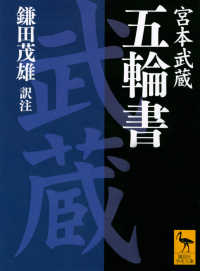
- 和書
- 五輪書 講談社学術文庫