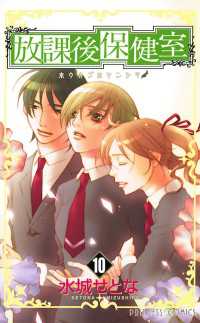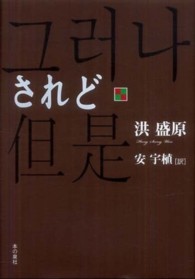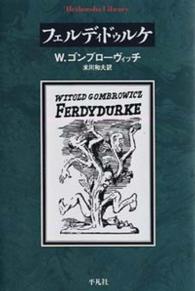出版社内容情報
柳田 国男[ヤナギタ クニオ]
著・文・その他
内容説明
かつて人々は、どのように火を使い、暗闇を照らしてきたのか。照明・煮炊き・暖房ほか、火にまつわる道具や風習の実例を丹念に集め、日本人の生活史を辿る。暮らしから次々と明かりが消えていく戦時下、「火の文化」の背景にある先人の苦心と知恵を見直した意欲作。
目次
やみと月夜
ちょうちんの形
ろうそくの変遷
たいまつの起こり
盆の火
燈篭とろうそく
家の燈火
油とあんどん
燈心と燈明皿
油屋の発生〔ほか〕
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫生まれ。1900年、東京帝国大学法科大学卒。農商務省に入り、法制局参事官、貴族院書記官長などを歴任。35年、民間伝承の会(のち日本民俗学会)を創始し、雑誌「民間伝承」を刊行、日本民俗学の独自の立場を確立。51年、文化勲章受章。62年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
39
人間の生活に火がどのように関わってきたのかを考察した本。提灯や蝋燭、行灯と火の変遷が語られており、昔の闇を駆逐しようとする動きが優しく語られている。これを書いている今、夜なので電気を消してみたが、遠くの灯りで部屋の中がぼんやりと見える。火の使い道は明かりだけではなく、木の摩擦から火打石のような火のつけ方、囲炉裏やかまどの調理に使う火。それ以外にも盆の送り火や、家庭における女性の火の管理なども語られていて興味は尽きない。スイッチ一つで付く今と違い、古人にとってその管理は一大事だったという事を認識させられた。2013/08/05
roughfractus02
4
超越神から火を獲得する神話を世界中から集めたフレイザー『火の起源の神話』を念頭に置くと、闇の深さと人間の警戒心を神や霊に投影して神聖な行事にも火を焚いて迎えたという説を披露する著者は、神を人間と似ている存在として扱う日本の文化の独自性を語っていることがわかる。一方、著者は竈門を巡る資料から、男女の分業制を日常で火を扱う役割が女性となった点に見る。さらに、大きな文字の書物を暗い夜に油煙塗れで読書した昔から現代までの灯火の歴史が語られると、読者は本書が灯火管制下の戦中(1944)に刊行されたことを思い起こす。2025/02/14
てれまこし
3
戦時中の灯火管制下、青少年、特に女性を対象に、火の使用に関する歴史が語られる。当り前のものが当たり前ではなくなったことを奇貨として、若者に史心を育てようという試みである。灯火や囲炉裏、竈など身近なものの話で読者の注意を向け、燃料という経済問題へ視野を広げ、最後は大東亜圏の他民族への同情と関心をさそうという考えられた構成になっている。そこで語られる歴史は進歩の歴史であるが、その進歩とは運命でも偉人の業績でもなく、庶民が生活を改善しようと試行錯誤してきた結果である。この事業を引き継ぐのは読者自身なのである。2018/02/06
bouhito
3
火というのは、結局よくわからない。人間を生かしもするし、殺しもする。物質ではない。現象である。人間は常に火とともに生きてきた。生活に火は必需品だった。しかし、そう言えるのもいつまでだろうか。昔、火があった、と言う時代が来てしまうかもしれない。2016/01/09
ダージリン
2
当たり前だが電気、ガスが無い時代には、火は生活の中で重要な位置を占める。嘗ては火を絶やさぬように注意を払ったというのも頷ける。過去の生活の一端が垣間見え、道具などの工夫の変遷も見えて興味深い。神事では石炭などは焚かずに、松が使われるという記載があるが、火と信仰はしっかりと結びついてもいるのであろう。2018/02/06