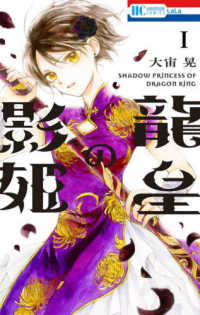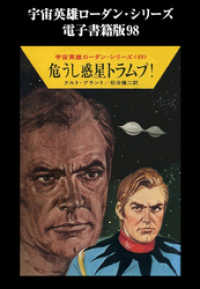内容説明
源頼朝に「日本一の大天狗」と言われた後白河院。したたかに乱世を生き抜いた帝王は、今様と呼ばれた流行歌謡に夢中になり、歌詞を集めて『梁塵秘抄』を編んだ。子どもを思う親心、男に裏切られた女の嘆き、地蔵菩薩や千手観音への信仰心、蝸牛や蟷螂への親愛感、都会のファッションへの興味―。ここには多様な世界が広がっている。本書は『梁塵秘抄』本文の抄出に現代語訳と解説を付し、今様の世界へ誘う入門書。
目次
梁塵秘抄巻第一(長歌;古小柳;今様)
梁塵秘抄巻第二(法文歌;四句神歌;二句神歌)
梁塵秘抄口伝集巻第十(今様耽溺の日々;乙前の死;二度目の熊野参詣;今様即仏道)
著者等紹介
植木朝子[ウエキトモコ]
1967年生まれ。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科単位取得。博士(人文科学)。現在、同志社大学文学部教授。専攻は中世歌謡(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
れみ
56
平安時代の流行歌謡・今様を後世に残そうと、後白河院によって編まれたもの。音を残すことが出来なかった時代の流行歌なので、時の権力者がこれにハマってなければ読むことすら出来なかったものもいっぱいあるんだろうなあと思うと、なかなか貴重なものだろうと思う。あと、大河ドラマ「平清盛」が好きでずっと見てたので「遊びをせんとや…」を読むと松田翔太くんの歌声を今でも思い出す。2015/02/19
saga
48
かの有名な「遊びをせんとや生まれけむ…」が収録された梁塵秘抄。しかし、自分の解釈=遊びをするために生まれたのだ、というのが誤っていたことを確認。白拍子、遊女、傀儡が謡う今様という当時の流行歌を、芸術の域に引き上げようと尽力した後白河院だったが、鎌倉時代に衰微してしまう。梁塵秘抄および口伝集20巻のほとんどが散逸し、謡い方も伝わらなかったのは惜しいことだ。後白河院というと陰の権力者というイメージがあったが、宗教心が篤く、芸能に関しては上下の身分を問わない人柄に好感が持てた。2024/09/23
うりぼう
27
松丸本舗、三冊屋の2冊目。後白川院、大物。院政を敷きながら、今様に耽溺し、師匠の最期に謳って、落涙させる。政治も今様も人のすること、人間が判り、時代が解り、哀しみが分かれば誤らない。今様は、現代のヒップホップであり、演歌であり、怨歌。宗教、庶民、哲学、自然を写し、娯楽と教養の粋。その聞きがきを後世に残すことが、彼の天命。梁りの塵に秘られた人間の惑いを映す。15夜に渡る今様合は、現代の紅白歌合戦。真央ちゃんも落涙。読書をせんとや生まれけむ、飲み会せんとや生まれけん、読メの仲間の声聞けば、私オフ会行くわいな。2012/01/27
fseigojp
22
このあたりで文芸の主役が貴族でなくなるようだ 鎌倉・室町で一大発展した歌舞音曲とりわけ能楽は今様同様に卑賤の身分のものたちの遊芸だった 江戸時代になると、もっと顕著に町人文芸が勃興する2016/08/31
たけはる
10
大河ドラマ平清盛に今さらハマり、見ていたら読みたくなりました。遊びをせんとや~はつい口ずさんでしまう。また、詩関連の本を読んでいると自分も短歌やら詩やらを作りたくなります。 あかつきあした、つとめての/ くがねてりはゆ、みあかしを/ をがみとなへば、たひらかに/ ひかりのいとは、くだりこむ/ さやさやに/ さやけきいとの、はやせして/ ながるるたきは、ふちとなり/ ゆたにたゆたに、うみぞなる/ とほながきこそ、たふとけれ/ いとたふと/ たふとや/ かみのあはれみなれば/2020/08/14