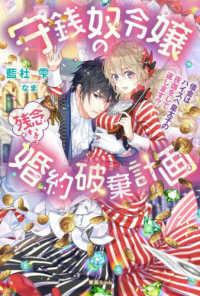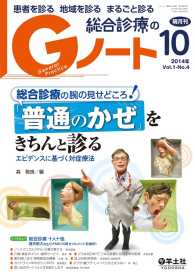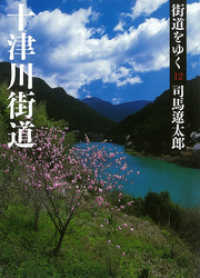- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
クリスマスにはなぜ贈り物をするの? 20世紀最大の人類学者がときあかす戦後フランスで巻き起こったサンタクロース論争を起点に、現代社会における大人と子ども、死者と生者、そして人類にとっての贈与の意味に切り込んでいく。日仏の人類学者が競演するクリスマス論の名著、新装版。
クロード・レヴィ=ストロース[クロードレヴィストロース]
1908年生まれ。フランスの人類学者。構造言語学の概念や方法を人類学に取り入れることによって親族関係や神話を解明。その手法は広く人文社会科学に影響を与え、構造主義の時代を切りひらいた。著書に『悲しき熱帯』『野生の思考』などがある。2009年、没。
中沢 新一[ナカザワ シンイチ]
1950年生。明治大学野生の科学研究所所長。東京大学大学院人文科学研究科博士過程満期退学。思想家、人類学者。『アースダイバー』『大阪アースダイバー』『野生の科学』(全て講談社)、『僕の叔父さん 網野善彦』『日本の大転換』(共に集英社新書)、『古代から来た未来人 折口信夫』(ちくまプリマー新書)、『チベットのモーツァルト』『森のバロック』(共に講談社学術文庫)、『三万年の死の教え』(角川ソフィア文庫)など著書多数。近著に『吉本隆明の経済学』(筑摩選書)、『日本文学の大地』(KADOKAWA)がある。
内容説明
クリスマスに、贈り物をするのはなぜ?一九五二年、サルトルの依頼で寄稿された論文「火あぶりにされたサンタクロース」。それは、クリスマスの新習慣を分析することで、資本主義化された社会における贈与の意味、そして幸福の問題へと深く切りこむものだった。
著者等紹介
レヴィ=ストロース,クロード[レヴィストロース,クロード] [L´evi‐Strauss,Claude]
1908年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。人類学者。パリ大学卒業後、哲学教授資格を得て1935年にサンパウロ大学教授として赴任。1941年には、ニューヨークの社会研究新学院教授として米国へ亡命。1959年、パリのコレージュ・ド・フランス教授として社会人類学の講座を創設する。1982年に退官し、2009年没
中沢新一[ナカザワシンイチ]
1950年生まれ。思想家、人類学者。明治大学野生の科学研究所所長。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
サアベドラ
ココロココ
白玉あずき
マツユキ