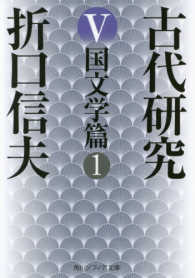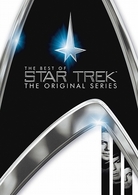出版社内容情報
折口学について自ら批判・分析した「追い書き」と13篇の論文を収録!「日本の『神』は、昔の言葉で表せば、たまと称すべきものであった」??。霊魂、そして神について考察した「霊魂の話」や、文献に残る絵図とともに詳説した「河童の話」、折口古代学の核心に迫る「古代人の思想の基礎」など十三篇を収録。巻末には、『古代研究』に収められたそれぞれの論文の要旨の解説にくわえ、「折口学」の論理的根拠と手法について自ら分析・批判した「追ひ書き」も掲載。
解説・加藤守雄/安藤礼二
【もくじ】
呪詞及び祝詞
霊魂の話
たなばたと盆祭りと
河童の話
偶人信仰の民俗化並びに伝説化せる道
組踊り以前
田遊び祭りの概念
古代人の思考の基礎
古代に於ける言語伝承の推移
小栗判官論の計画 「餓鬼阿弥蘇生譚」終篇
漂着石神論計画
雪まつりの面
「琉球の宗教」の中の一つの正誤
追い書き
解説 折口信夫研究 加藤守雄
新版解説 霊魂としての神 安藤礼二
収録論文掲載一覧
「日本の『神』は、昔の言葉で表せば、たまと称すべきものであった」??。霊魂、そして神について考察した「霊魂の話」や、文献に残る絵図とともに詳説した「河童の話」、折口古代学の核心に迫る「古代人の思想の基礎」など十三篇を収録。巻末には、『古代研究』に収められたそれぞれの論文の要旨の解説にくわえ、「折口学」の論理的根拠と手法について自ら分析・批判した「追ひ書き」も掲載。
解説・加藤守雄/安藤礼二
【もくじ】
呪詞及び祝詞
霊魂の話
たなばたと盆祭りと
河童の話
偶人信仰の民俗化並びに伝説化せる道
組踊り以前
田遊び祭りの概念
古代人の思考の基礎
古代に於ける言語伝承の推移
小栗判官論の計画 「餓鬼阿弥蘇生譚」終篇
漂着石神論計画
雪まつりの面
「琉球の宗教」の中の一つの正誤
追い書き
解説 折口信夫研究 加藤守雄
新版解説 霊魂としての神 安藤礼二
収録論文掲載一覧
折口 信夫[オリクチ シノブ]
1887年?1953年。国文学者、民俗学者、歌人、詩人。歌人としての名は「釈迢空」。大阪府木津村生まれ。天王寺中学卒業後、國學院大學に進み、国学者三矢重松から深い恩顧を受ける。國學院大學教授を経て、慶應義塾大学教授となり、終生教壇に立った。古代研究に基を置き、国文学、民俗学の域に捉われることなく、広く学問研究と表現活動を続けた。代表作に『古代研究』『口訳万葉集』『死者の書』、歌集に『海やまのあひだ』『倭をぐな』(角川ソフィア文庫『釈迢空全歌集』に収録)等がある。没後、日本芸術院恩賜賞を受賞。
内容説明
「日本の『神』は、昔の言葉で表せば、たまと称すべきものであった」―。霊魂、そして神について考察した「霊魂の話」や、文献に残る絵図とともに詳説した「河童の話」、折口古代学の核心に迫る「古代人の思考の基礎」など十三篇を収録。巻末には、『古代研究』に収められたそれぞれの論文の要旨の解説にくわえ、「折口学」の論理的根拠と手法について自ら分析・批判した「追い書き」も掲載。
目次
呪詞及び祝詞
霊魂の話
たなばたと盆祭りと
河童の話
偶人信仰の民俗化並びに伝説化せる道
組踊り以前
田遊び祭りの概念
古代人の思考の基礎
古代に於ける言語伝承の推移
小栗判官論の計画「餓鬼阿弥蘇生譚」終篇
漂着石神論計画
雪まつりの面
「琉球の宗教」の中の一つの正誤
追い書き
著者等紹介
折口信夫[オリクチシノブ]
1887(明治20)年~1953(昭和28)年。国文学者、民俗学者、歌人、詩人。歌人としての名は「釈迢空」。大阪府木津村生まれ。天王寺中学卒業後、國學院大學に進み、国学者三矢重松から深い恩顧を受ける。國學院大學教授を経て、慶應義塾大学教授となり、終生教壇に立った。古代研究に基を置き、国文学、民俗学の域に捉われることなく、広く学問研究と表現活動を続けた。没後、全集にまとめられた功績により日本芸術院恩賜賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
roughfractus02
あかつや