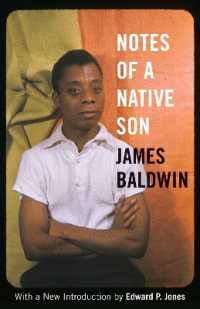出版社内容情報
本能を震わす、メロディの秘密。ゴジラ音楽の原点を明かす!真の美しさを発見するためには、
教養と呼ばれるものを否定する位の心がまえが必要です――。
土俗的なアイヌ音楽に影響を受け、
日本に根ざす作品世界を独学で追求した作曲家、伊福部昭。
語りかけるように綴られた音楽芸術への招待は、
聴覚は最も原始的な感覚であり、本能を揺さぶるリズムにこそ
本質があるとする独自の音楽観に貫かれている。
「ゴジラ」など映画音楽の創作の裏側を語った貴重なインタビューも収録。
解説:鷺巣詩郎
[目次]
序
はしがき
第一章 音楽はどのようにして生まれたか
第二章 音楽と連想
第三章 音楽の素材と表現
第四章 音楽は音楽以外の何ものも表現しない
第五章 音楽における条件反射
第六章 純粋音楽と効用音楽
第七章 音楽における形式
第八章 音楽観の歴史
第九章 現代音楽における諸潮流
第十章 現代生活と音楽
第十一章 音楽における民族性
あとがき
一九八五年改訂版(現代文化振興会)の叙
二〇〇三年新装版(全音楽譜出版)の跋
インタビュー(一九七五年)
解説 鷺巣詩郎
序
はしがき
第一章 音楽はどのようにして生まれたか
第二章 音楽と連想
第三章 音楽の素材と表現
第四章 音楽は音楽以外の何ものも表現しない
第五章 音楽における条件反射
第六章 純粋音楽と効用音楽
第七章 音楽における形式
第八章 音楽観の歴史
第九章 現代音楽における諸潮流
第十章 現代生活と音楽
第十一章 音楽における民族性
あとがき
一九八五年改訂版(現代文化振興会)の叙
二〇〇三年新装版(全音楽譜出版)の跋
インタビュー(一九七五年)
解説 鷺巣詩郎
伊福部 昭[イフクベ アキラ]
1914年、北海道生まれ。作曲家。独学で作曲をはじめ、道庁に勤務するかたわらオーケストラ「日本狂詩曲」を発表し、以後、アイヌなどの民族音楽をとりいれた作風を展開。1946年からは東京音楽学校(現・東京藝術大学)で教鞭をとり、芥川也寸志らを指導した。管弦楽曲や器楽曲にとどまらず、映画「ゴジラ」「ビルマの竪琴」などの劇中音楽でも知られている。2006年没。
内容説明
土俗的なアイヌ音楽に影響を受け、日本に根ざす作品世界を独学で追求した作曲家、伊福部昭。語りかけるように綴られた音楽芸術への招待は、聴覚は最も原始的な感覚であり、本能を揺さぶるリズムにこそ本質があるとする独自の音楽観に貫かれている。「ゴジラ」など映画音楽の創作の裏側を語った貴重なインタビューも収録。
目次
第1章 音楽はどのようにして生まれたか
第2章 音楽と連想
第3章 音楽の素材と表現
第4章 音楽は音楽以外の何ものも表現しない
第5章 音楽における条件反射
第6章 純粋音楽と効用音楽
第7章 音楽における形式
第8章 音楽観の歴史
第9章 現代音楽における諸潮流
第10章 現代生活と音楽
第11章 音楽における民族性
著者等紹介
伊福部昭[イフクベアキラ]
1914年、北海道生まれ。作曲家。北海道帝国大学農学部林学実科卒業。35年、北海道庁の林務官として勤務するかたわら作曲した「日本狂詩曲」でチェレプニン賞第一席入賞。アイヌなどの民族音楽に学んだ独自の作風を展開し、37年に「土俗的三連画」、43年に「交響譚詩」を発表。戦後は東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で教鞭をとり、芥川也寸志、黛敏郎、矢代秋雄などの後進を育てた。声楽曲「ギリヤーク族の古き吟誦歌」、舞踊曲「人間釋迦」、交響曲「シンフォニア・タプカーラ」のほか、「ゴジラ」シリーズや「ビルマの竪琴」などの映画音楽を数多く手がける。2006年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あやの
らぱん
あちゃくん
ナマアタタカイカタタタキキ
1959のコールマン
-

- 電子書籍
- 復讐アイドルー姉を殺した犯人に仕返しし…