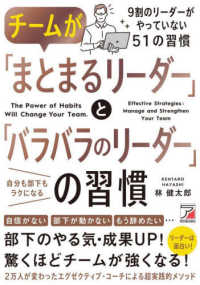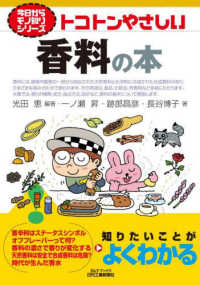内容説明
「神隠し」とは人を隠し、神を現わし、人間世界の現実を隠し、異界を顕すヴェールである。それは人を社会的な死、つまり「生」と「死」の中間的な状態に置く装置であった。だからこそ「神隠し」という語には甘く柔らかい響きがただよう―。異界研究の第一人者が、「神隠し」をめぐるフォークロアを探訪し、日本人の異界コスモロジーを明らかにする。
目次
第1章 事件としての神隠し(村の失踪事件;帰ってきた失踪者 ほか)
第2章 神隠しにみる約束ごと(神隠し譚の類型;夕暮れどき ほか)
第3章 さまざまな隠し神伝説(民俗社会の異界イメージ;隠し神としての天狗イメージ ほか)
第4章 神隠しとしての異界訪問(浄土=ユートピアとしての異界;夢と異界訪問譚 ほか)
第5章 神隠しとは何か(現代の失踪事件;「神隠し」のヴェールを剥ぐ ほか)
著者等紹介
小松和彦[コマツカズヒコ]
1947年、東京都生まれ。東京都立大学大学院社会人類学博士課程修了。信州大学助教授、大阪大学教授を経て、現在、国際日本文化センター教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イトノコ
27
キンドル合冊版。民俗社会における神隠しについて。神隠しは原因のわからない行方不明に理由をつけるために働く装置ということ、その点では妖怪と同じようなものか。失踪者側がが隠したい失踪の理由を不問にする寛容的な側面があったと言うのは意外。現代で例えると「俺は東京でビッグになるぜ!」と故郷を飛び出したが夢破れて帰ってきたケースとか、駆け落ちしたけど上手くいかず出戻ってきたケースなども再び共同体に迎え入れられると言うことか。しかし共同体内での誘拐・殺人などを隠す負の側面も強かったのではないかと想像してしまう。2023/12/14
テツ
21
共同体から突然人が消える。理由がなく共同体から仲間が消えてしまったら不安になるのでどうにかこうにか説明をつけようとする。曰く、神に隠された。天狗に攫われた。旅の六部に勾引かされた。こうした共通認識があればその人間が戻ってきて共同体に復帰するときも確かにきもち的に楽だよなあ。だって神様に隠されていたんだもん。本人の意思による失踪とは明らかに異なる。現代的な価値観から読み解いているからかもしれないけれど、優しいシステムだなあと感心しました。ああ確かに『神隠し』だ。2019/11/29
風竜胆
16
近代合理性だけに支配される世の中は味気ない。著者は最後の方で、<現代こそ実は「神隠し」のような社会装置が必要なのではないか>と括っている。しかし、「神隠し」に代るようなものを現代社会に見出すことができるのだろうか。 2013/06/29
佐倉
15
“神隠し”として語られる現象のパターンを見ていきながら、民俗社会における意義を探っていく。 怨霊にしろ妖怪にしろそれが“ある”とされた社会においてそれぞれ一定の役割があったわけだが、神隠しは人間の失踪(とそれによって予想される死)を“隠す”機能があったとしている。人浚い、婚姻関係、あるいは特に意味の無い失踪。いずれにしろそこにあったものを直視しないことで社会を回すためのものとして存在していた。一種のセラ ピーのようなものだったのだろう。2024/01/17
aochama
13
高度成長期とともに語られることのなくなった神隠し。かつての神隠し話を丁寧に分析。実は厳しい社会の現実を包み生死の中間的状態におくことで一旦社会的に死んだこととし、戻って来るときは、社会的再生として受け入れ易くする社会装置であるとします。そして現代こそこの装置が必要ではないかと言います。 確かに。明確な答えを出さずに一旦仮おきしたストーリーで納める。先送りといえばそうなんですが、余裕のない現代を精神的に住みやすくするには、このような豊かな発想が求められているのではないかと思いましたね。2019/06/09
-
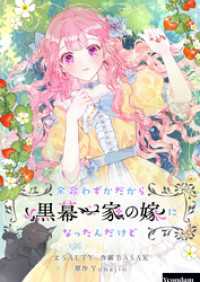
- 電子書籍
- 余命わずかだから黒幕一家の嫁になったん…
-

- 電子書籍
- 改訂新版 保育カウンセリングへの招待