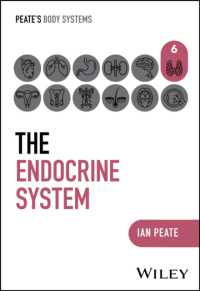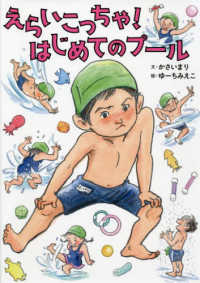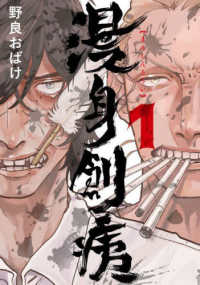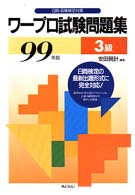内容説明
現代日本語の和語を見たとき、現代語としては一語となっていても、実は幾つかの古語の要素から構成されているものが多い。そのようなものを100項取り立てて、本来どういう意味で、どういう由来をもち、どういう変遷をたどって今日に至っているのか、古典・現代の用例を引きながら説き明かす。
目次
「足立」「鐙」の「あ」―「足」の古称で、現代語の「あし」
「あだおろそかに」の「あだ」―「おろそかに」と同義で、「いいかげんだ」
「新手」「新仏」の「あら」―古典語「新たなり」の「新」で「あたらしい」
「あるいは」の「い」―主語を強調した、きわめて古い時代の助詞
「いぎたない」の「い」―「ねること」を意味した名詞〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
宙太郎
0
例えば”口さがない”の”さが”のような複合語の構成要素に着目して、その由来を古典の用例から考えるといった構成がユニーク。とは言え、内容は高校の古典の授業の延長といった印象でかなり真面目。本当に「読みもの」? 著者が「はじめに」で「OLの皆さまには、お茶の時間の話題のひとつに」なんて書いてあるのを見てちょっと笑ってしまった。3時にコーヒー飲みながら「ねぇねぇ、古語の”生く”には四段活用と上二段活用と下二段活用の3種類あってさぁ…」なんて話をしている会社ってどこにあるんだ? でも、僕には面白かったんだなぁ…2024/11/01