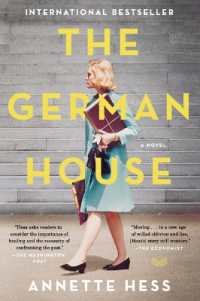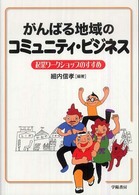内容説明
西欧列強のアジア侵略が激化し始めた20世紀初頭、インド仏跡の巡拝と海外における宗教活動の視察のためロンドンに赴いた大谷光瑞は、ヨーロッパの各国が国を挙げて東洋学に取り組んでいるのを目のあたりにし、衝撃を受ける。「キリスト教徒が仏教の遺跡を探検しておるというのに、われわれが坐視するわけにはいかん」国家的大事業である西域探検を西本願寺という一教団の力で押し進め、世界を驚嘆させた浄土真宗第二二代門主、大谷光瑞の波瀾万丈の行動の軌跡を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
8
明治35年から3回にわたって、シルクロード探検を決行した光瑞。当時の探検家と言えば、ヘディンが最も有名だが。光瑞は西本願寺の財力を持って「仏教国に生きる人間の矜持」を賭けたのだろうか。そのころの西本願寺と言えば財力から言っても猛烈な資材を有しており、彼なら出来たであろう。その発掘行動は色々非難が集中する事もあったが多くの財宝を持ち帰り、結果西本願寺は傾く。そのやり取りはすべてではないが小説としての作品中に散見して伺える。あくまでもベールに包まれている・・と割り切って読むモノだろう。
ヨシモト@更新の度にナイスつけるの止めてね
4
探検隊員の手記などは読んでいたが、そこからこんなにも詳細かつ読んでワクワクする冒険譚を書き上げる津本陽はすごい。さすがは職業作家だ。知りたかったのは、彼が失脚後アジアに出て何をしていたかなのだが、この本を読んでいる間中、幸せだったので、まぁよしとしよう。しかし彼の後半生を知るには、何を読めばいいのかな。2016/10/13
mun54
3
とてもスケールが大きく、大谷探検隊など宗教界に大きな功績を残した人物。 明治時代、西本願寺と京都市の年間予算が同じ位の金額というのに驚いた。2014/12/14
S‐tora
2
◎ 生涯ではなく、半生。 セレブリティの模範みたいな人だけども、時代の流れに翻弄されて、志半ばで挫折していくところがとても切ない。2016/07/06
可兒
2
近代一の本願寺門主の話。現門主いわく「型にはまらない人」だったらしいが、読んだ今では笑いとともにうなずける2011/04/15