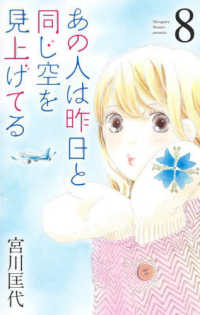内容説明
農民兵士を傭兵に、同族主義を実力主義に、多くの慣習を次々と変えて乱世を勝ち抜いた信長。「人たらし」と呼ばれるほどの対人交渉術と謀略の才で、最高の出世を果たした秀吉。生涯幾度もの苦難と失敗を重ね、腰が低く誰からも慕われた家康。軍備のみならず、政治、経済、社会そして信仰に至るまで、戦国の常識を打ち破った三傑の生き様から、見えてくるものは何か?固定観念を取り払い、歴史の細部に隠されている真実に迫る。
目次
織田信長
豊臣秀吉
徳川家康
著者等紹介
井沢元彦[イザワモトヒコ]
1954年名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、TBS報道局に入社。在職中の80年に『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞し、作家デビューを果たす。退社後、執筆活動に専念。独自の歴史観からテーマに斬り込む作品で人気を博している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
144
信長・秀吉・家康についての解釈。とはいえ時代を開いたのは信長であった。戦国の世に突如出現した革命児。打倒した最大の相手は当時の政治経済の既得権者である寺社勢力と常識。当時は紙や油等の製法は寺社が大陸より得ており、製造をするには寺社の許認可と金銭の支払いが必要だった。楽市楽座は寺社勢力とぶつかる。経済政策の成功により傭兵の常備軍を組織した信長。延暦寺焼討ちや本願寺との11年戦争により、寺社勢力の政治介入を終結させる。そして朝廷の権威によらぬ統治の為に自ら神を名乗る。本能寺の変がなければ、未知の日本があった。2018/02/04
アイゼナハ@灯れ松明の火
36
通史では書き落とされがちな登場人物のトピックを綴った井沢版戦国武将列伝。流石に有名どころのこのお三方で目新しい話はないだろう、と思ってましたが、信長の寺社勢力との対立の根底には、商業の権益を巡る争いがあったという観点には目からウロコが落ちた思い。宗教弾圧ではなく武装解除だったんだ、と言われてみれば成程って感じ。歴史は奥が深いなぁ。まだまだ修行が足りませぬ。2012/04/01
gonta19
31
2009/3/30 新大阪のBooks Kioskで購入。 2013/4/22〜4/27 戦国時代の三傑、信長、秀吉、家康についての評論。基本的には、井沢さんが、いろいろなところで書いている事の再構成だが、信長の商人としての才能、秀吉の極悪人性、家康の心情など、違った切り口で歴史を垣間見させてくれる。久しぶりに感動した内容。2013/04/27
maito/まいと
20
井沢流、天下三英傑解釈本。毎度のことながら、井沢本はテーマ本になると口調が穏やかになる(笑)今回もその例外に漏れず、分析に留まってしまうのが物足りない(まあ、なぞっていない分、他の研究本よりマシなんだけど)2013/07/02
Yukihiro Nishino
19
相変わらずの井澤節前回の書。なかなか説得力のある説だと思うが、人によっては独善的と映るかも。2016/01/18
-
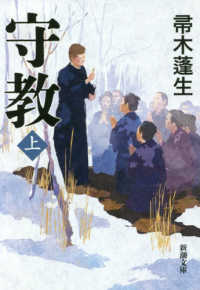
- 和書
- 守教 〈上〉 新潮文庫