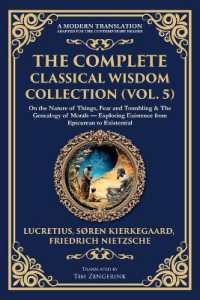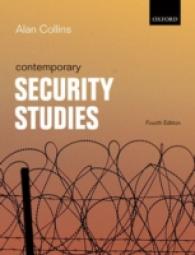出版社内容情報
『イノセント・デイズ』を今一度書く。そして「超える」がテーマでした。僕自身はその確信を得ています――早見和真
長い間歪み続けた愛や母性の歴史、地層のように積み重なる闇に確かな兆しを探し続けた。神なるものへの幻想と呪縛を解き放つ祈りとその熱に、心が確かに蠢いた。――池松壮亮(俳優)
私も命を繋いでいく役目を担うのだろうか。微かな光と絶望に怯えながら、夢中で読み進めた。どうしようもない日々に、早見さんはいつだって、隣で一緒に座り込んでくれるんだ。――長濱ねる(タレント)
自分の奥底に隠しておきたい暗い何かをわかってくれている、という書き手がこの世に一人でもいること。そのことに救われ、気持ちが軽くなる読者は少なくはない。――窪美澄(小説家)
容赦などまるでない。「母」にこだわる作家が、母という絶対性に対峙した。確かなものなど何ひとつない世の中で、早見和真は正しい光を見つけようとしている。その試みには、当然異様な熱が帯びる。――石井裕也(映画監督)
ラストに現れるヒロインの強い覚悟と意思の力に、私たちは元気づけられる。辛く暗く苦しい話だが、そういう発見があるかぎり、小説はまだまだ捨てたものではない。――北上次郎(書評家)(「カドブン」書評より抜粋)
八月は、血の匂いがする――。愛媛県伊予市に生まれた越智エリカは、この街から出ていきたいと強く願っていた。男は信用できない。友人や教師でさえも、エリカを前に我を失った。スナックを営む母に囚われ、蟻地獄の中でもがくエリカは、予期せず娘を授かるが……。あの夏、あの団地の一室で何が起きたのか。嫉妬と執着、まやかしの「母性」が生み出した忌まわしい事件。その果てに煌めく一筋の光を描いた「母娘」の物語。
内容説明
八月は、血の匂いがする―。愛媛県伊予市に生まれた越智エリカは、この街から出ていきたいと強く願っていた。男は信用できない。友人や教師でさえも、エリカを前に我を失った。スナックを営む母に囚われ、蟻地獄の中でもがくエリカは、予期せず娘を授かるが…。あの夏、あの団地の一室で何が起きたのか。嫉妬と執着、まやかしの「母性」が生み出した忌まわしい事件。その果てに煌めく一筋の光を描いた「母娘」の物語。
著者等紹介
早見和真[ハヤミカズマサ]
1977年神奈川県生まれ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。同作は映画化、コミック化されベストセラーとなる。15年『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を、20年『ザ・ロイヤルファミリー』で第33回山本周五郎賞と2019年度JRA賞馬事文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
misa*
くりん
うどん
yuuguren
-

- 和書
- 合本公害原論 (新装版)