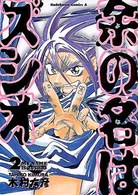内容説明
今や世界最大のヘッジファンドと評される第一次産業中央金庫。憧れの銀行員を夢見て産中に就職した城山良太は、研修先の淡路島の長閑な光景に衝撃を受ける。そこには都会の金融業界とは対照的な農業と寄り添う企業の姿があったのだ。翌年、営業部へと異動になった良太は、融資部門でかつてない業績を挙げ、頭角を現していくが―。2度の国家的な経済危機を乗り切った男の、発想と信念が、未曾有の混乱を生き抜く指針となる!
著者等紹介
波多野聖[ハタノショウ]
1959年、大阪府生まれ。一橋大学法学部卒業後、国内外の金融機関でファンド・マネージャーとして活躍する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まつうら
42
もしかしてこれは著者の自叙伝?と思って手に取った作品。農林中金の実態が、企業向け融資は下手くそながら、相場で稼ぐヘッジファンドであると論じているところはたしかに著者らしい。でも農林中金よりも都市銀行衰退のくだりがとても興味深い。銀行マンは、優良融資先を開拓するノウハウを代々伝授してきたが、1980年代のバブルはそれを伝授する機会も必要性も吹き飛ばした。バブル崩壊後に残されたのは、ノウハウを失った銀行マン。優良融資先など探せるはずもない。メガバンクに統合される段階で、都市銀行はすでにオワコンだったのだ。2022/09/17
Yunemo
22
農中系の仕組み、組織ってこうなっているんだ、と初めて知りました。タイトルの不可思議さを理解、でも黄金の稲とヘッジファンドの繋がりってちょっと難しいですね。一般の銀行と同様な感じでいましたから。資金の源泉がどこからきているか、また取り付け騒ぎが起こらない理由についても、そうなんだと改めて思い知った一冊です。この組織いろんな生き方があるんだとも。著者が文中で記す「産中での自分。あるべき自分。本来的な自分と本来的な産中」、組織で生きるための自身のスタンスをどうとっていくかということ。この生き方が難しいと実感。 2021/12/30
のぶ1958
12
フィクションでありながら自身の経歴を踏まえた内容かと思います。ファンドマネージャーとして成功を収めた著者が、自然環境がもたらす全てを穏やかに包み込む”空気”への憧れの様なものが伺えました。 --- 「天や海や大地からの恵みの理想」 稲穂の海は黄金のように輝いていた。2021/02/26
ダック
11
波多野さんの書かれた本を読むと仕事のやる気がでてくるのですが、この本も例に漏れずでした。今まで読んだ波多野作品でも一番好きかもしれません。2021/11/19
yamakujira
10
系統金融機関に就職した良太は、投資部門を統括する上司に見込まれてトレーダーとして活躍しながら、いつしか会社の存在意義と自分のスタンスに疑問を感じ始める。名前は変えてあっても農林中金がモデルだとわかるから、既得権益の牙城に見えて腹立たしい。単位農協の不良債権をマスコミ報道を抑えて処理すればお手柄だなんて、ひどい価値観だな。サラリーマン応援小説のふりをしてワーカホリックな働き方を称賛する物語は嫌いだけれど、そもそも物語がおもしろくなくて苦労して読了。プロローグになんの意味があるのだろう。 (★★☆☆☆)2022/02/04