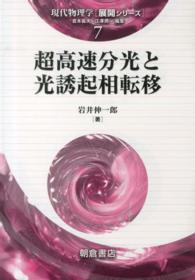出版社内容情報
【「横」は木(きへん)、「特」は牛(うしへん)はなぜ?】
「虹」はなぜ「虫」がつくのか、「零」はなぜ「雨」なのか……身近な部首の起源を探ると、古代中国の景色が見えてくる! 現在使われる214部首のうち約8割が誕生していた、中国史上最古の王朝・殷。当時の甲骨文字から、西周の金文・秦の篆書・中世の楷書へと、漢字は中国王朝史と共に変化を遂げてきた。甲骨文字研究の第一人者が、漢字の部首の成立の過程を辿り、文化、社会、自然観との関係性を解きほぐす。
「零」は「わずかに雨が降る」様子だった
「示」は祭祀用の机に供物が載っている
「酬」は本来「酒をすすめる」こと
「聖」は「よく聞く」人を讃えた文字
【目次】
はじめに──部首は古代世界の縮図
序 章 漢字の歴史──甲骨文字から楷書へ
第一章 部首の歴史──『説文解字』から『康煕字典』へ
□コラム 甲骨文字の部首と配列
第二章 動植物を元にした部首──「特」別な牛、竹製の「簡」
□コラム そのほかの動植物を元にした部首
第三章 人体を元にした部首──耳で「聞」く、手で「承」ける
□コラム そのほかの人体を元にした部首
第四章 人工物を元にした部首──衣服の余「裕」、完「璧」な玉器
□コラム そのほかの人工物を元にした部首
第五章 自然や建築などを元にした部首──「崇」は高い山、「町」は田のあぜ
□コラム そのほかの字素の部首
第六章 複合字の部首──より多様な概念の表示
□コラム そのほかの複合字を元にした部首
第七章 同化・分化した部首──複雑な字形の歴史
□コラム そのほかの同化・分化した部首
第八章 成り立ちに諸説ある部首──今でも続く字源研究
□コラム 字源のない部首
おわりに──漢字の世界の広がり
索引
内容説明
文字を組み合わせることで多様な意味を表現できる「漢字」。その基となる214部首のうち約8割は、3千年以上前の中国史最古・殷王朝ですでに出現していた―身近な部首の疑問を通じて、古代の文化と社会に迫る!
目次
序章 漢字の歴史―甲骨文字から楷書へ
第1章 部首の歴史―『説文解字』から『康熙字典』へ
第2章 動植物を元にした部首―「特」別な牛、竹製の「簡」
第3章 人体を元にした部首―耳で「聞」く、手で「承」ける
第4章 人工物を元にした部首―衣服の余「裕」、完「璧」な玉器
第5章 自然や建築などを元にした部首―「崇」は高い山、「町」は田のあぜ
第6章 複合字の部首―より多様な概念の表示
第7章 同化・分化した部首―複雑な字形の歴史
第8章 成り立ちに諸説ある部首―今でも続く字源研究
著者等紹介
落合淳思[オチアイアツシ]
1974年、愛知県生まれ。立命館大学大学院文学研究科史学専攻修了。博士(文学)。現在、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員。専門は甲骨文字と殷代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
山中鉄平
Teo
なつみかん
インテリ金ちゃん
-
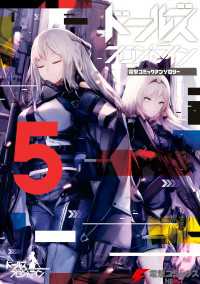
- 電子書籍
- ドールズフロントライン 電撃コミックア…