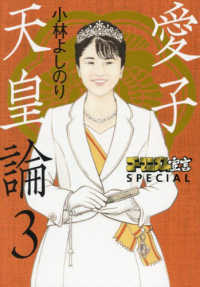内容説明
瀬戸内の小領主から備前美作両国を治める大大名になった宇喜多氏。“表裏第一ノ邪将”と呼ばれた父・直家の後を継ぎ、宇喜多秀家は若くして豊臣政権の「大老」にまで上りつめる。しかし、その運命は関ヶ原での敗北を境にして一変。ついには八丈島に流罪となる。激動の時代を生き抜いた執念の男の生涯はどのようなものだったのか。最新研究をもとに実像を描きだす決定的評伝!
目次
第1章 戦国乱世の終焉(大名権力宇喜多氏の誕生;天下統一)
第2章 期待の若武者(異例の厚遇;第一次朝鮮出兵)
第3章 豊臣政権の黄昏(岡山城・城下町の整備と惣国検地;関白秀次事件と第二次朝鮮出兵)
第4章 栄華の果て(宇喜多騒動と関ヶ原合戦;没落大名のそれから)
著者等紹介
大西泰正[オオニシヤスマサ]
1982年岡山市生まれ。2007年京都教育大学大学院修了。現在は石川県金沢城調査研究所所員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
terve
26
筆者は宇喜多政権の特徴として「特殊性」と「脆弱性」を挙げています。それは経験不足・実力不足を秀吉の威光で補うが、秀吉が倒れるとその全てが無に帰すということです。五大老の中でも扱いが軽いという指摘もありましたが、それだけ気兼ねなく扱えるという見方もできそうです。いずれにせよ、秀吉が転けたことが秀家にとっての不幸であって、それは何より実力不足であったことの証左かと思います。そういえば「宇喜多備前中納言八郎秀家。豊臣家の御危機を聞き、八丈島より泳 い で 参 っ た!!」と、こんなネタを思い出しました。2019/09/21
サケ太
21
五大老として、関ヶ原で敗北した大名として名を残す宇喜多秀家。彼の出生から(直家はあっさりめ)、豊臣政権で重用されていったのかが書かれている。豊臣大名としての秀家。宇喜多家の特色や騒動の起きた原因も興味深い。兄と対比して穏やかで慎重な人物といわれていた宇喜多忠家やその息子浮田左京亮の人物像が衝撃的。頼りにならないし、しないほうが良いというのは正しい。改易後の生活が続けられた理由についても答えが出ており、面白い。利用できるものは利用しつくしている感覚がとても良い。“宇喜多一類”の見方やその魅力に気がつけた。2019/09/19
ようはん
17
次代の豊臣政権の重鎮として秀吉から多大な期待をかけられて優遇され可愛がられた秀家ではあるけど、結局若さ故の経験不足にそれを補える程の俊英でもなかった為にその期待には応えられなかった感。家中のゴタゴタの最中に後ろ盾である秀吉と岳父の利家を相次いで失い、八丈島に流された後も息子が精神的に病んだりと不幸が多いんだよな。2019/12/22
MUNEKAZ
14
著者の前著『前田利家・利長』が面白かったので購入。秀家本は以前に渡辺大門先生のを読んだことがあるが、そこにあった宇喜多氏の出自や父・直家に関する部分はバッサリで、代わりに妻・樹正院について多くページを割いている。これが面白いポイントで、秀家の「貴公子」ぶりの後ろ盾となった豊臣・前田とのつながりや、没落後の前田家からの支援の理由が明確になっている。また頼りになるイメージの叔父・忠家に対して、著者が「短慮」と厳しい評価を下しているのも印象的であった(まぁ息子はいろいろとヤバい人物だしなぁ)。2019/09/10
田中峰和
12
宇喜多秀家は関ケ原で敗北したのが28歳の時、縁者を頼り除名嘆願するも6年後に八丈島に配流となった。父直家のおかげで30万石の大名となり、妻の豪姫(樹正院)が秀吉の幼女でお気に入りだったことも追い風となった。なんの実績もないのに、権中納言に任官、家康らと並ぶ五大老となる。豪姫が狐憑きに病んだときは秀家も焦っただろう。嫁が死ねば秀吉の贔屓は終わり政治的地位の維持は困難になる。指導力不足を補うため、秀吉は家臣団の叙位任官を勧め、主従関係を確立させた。まさに恩人の秀吉を裏切れない結果が50年の流人生活となった。2019/12/11
-
- 洋書
- Nosotros