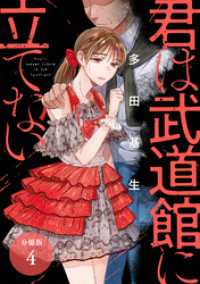内容説明
経済成長が最も優先された戦後の日本。豊かさと引きかえに、水や大気は徹底的に汚染され、森を奪われた動物たちは絶滅の危機に瀕した。それから30年余りで、目を見張るほどの再生を見せている。その陰では、市民、研究者、自治体職員が死力を尽くしていた。日本の環境を見続けてきた著者による唯一無二の書。
目次
第1章 鳥たちが戻ってきた(千羽鶴になったタンチョウ;孤島で全滅を免れたアホウドリ;大空を舞うガンの群れ ほか)
第2章 きれいになった水と大気(数字でみる環境改善;回復に向かう東京湾;多摩川にアユが踊る ほか)
第3章 どこへ行く日本の環境(日本人の生命観の変化;何が環境を変えたのか;環境を救ったものは ほか)
著者等紹介
石弘之[イシヒロユキ]
1940年東京都生まれ。東京大学卒業後、朝日新聞社入社。ニューヨーク特派員、編集委員などを経て退社。国連環境計画(UNEP)上級顧問を経て、96年より東京大学大学院教授、ザンビア特命全権大使、北海道大学大学院教授などを歴任。この間、国際協力事業団参与、東中欧環境センター理事などを兼務。国連ボーマ賞、国連グローバル500賞、毎日出版文化賞をそれぞれ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiyu
8
アホウドリ絶滅寸前や川の流れを変える話を読むと、悲しさを通り越す。人がその環境とかかわる場合、どこまで介入が可能かどうか。過剰な環境変化を行えば本書のような環境汚染が生じることになるだろうし、全く手を付けなければ現在の利便性は手に入れられただろうか。正直悩むところはある。2020/04/20
西澤 隆
7
「鉄条網の世界史」でのベルリンの壁の狭間などにできた生物聖域的状況の紹介からの流れで読む本書。僕の年代だと学校で習うのは致命的なまでの公害とその反省からの動きの「兆し」だったけれど本書冒頭部のアホウドリなどの事例では「そうはいってもずいぶんよくなった」ことが数多く示される。同じ場所を読んでも年代により受け取る印象はずいぶんちがうはず。後段に進むにつれ日本の成長戦略のために犠牲にされたものと「押し戻す」ための努力の数々が語られ、共感もある一方八ッ場ダムの顛末のように「本書のその後」に考え込んでしまうものも。2020/10/18
ふたば
6
明治維新からこっち、欧米諸国に追い付き追い越せ。。で来た日本は、ほんの少し前まで、環境破壊を進める劣悪国だったようだ。しかし、貴重な鳥たちが戻り、水は清らかさを取り戻しつつあるらしい。明治の工業化と、高度成長、バブルの時代が、環境破壊を進めた。空は煤煙に曇り、水は毒性を帯びた。森林は伐採され、保水力を失い、災害をもたらすようになった。それでも、人々は大企業や、政府、官僚たちとの厳しい対立を経ながら、少しずつ環境を改善してきた。人が快適に暮らそうと思うなら、自然はどうしても犠牲になる。2019/11/23
このこねこ@年間500冊の乱読家
3
⭐⭐⭐ 日本は他に類を見ないスピードで環境を壊し、他に類を見ないスピードで壊した環境を復活させました。 大戦後の不死鳥のような経済復興はもちろん素晴らしいですが、そこには環境の犠牲もあったことを知りました。 経済成長以外で日本が輝くことを考えるのも、良いかもですね。2022/02/08
夢読み
3
戦後を中心とした、近代化過程での公害・自然破壊とそこからの復興(まだ途上であろうが)がつづられている。復興に尽力された方々の苦労・努力には頭が下がるばかりであるが、激甚ともいえる公害の姿にも慄然とさせられる。さらに恐ろしいのはそうした公害は、ほぼ国是であったともいえることである。「当時はそうせざるを得ない状況だった」という、とある政治家の言葉が掲載されているが、それはおそらく嘘でないであろう言葉で、非常に暗い気持ちになる。2020/06/20