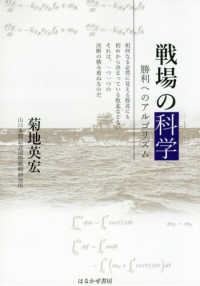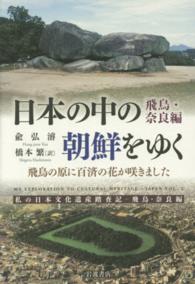出版社内容情報
すべての管理職必携。組織を伸ばす必須の力!いま、組織の中間管理職は受難の時代である。
「働き方改革」が叫ばれる一方で、成果については一段と厳しく問われる現場。
これを乗り切るための必要不可欠な心得、それは「部下の力を十二分に発揮させること」である。
部下の意欲を引き出すためのコミュニケーションのとり方や、組織の根幹となる「信頼と志」の重要性などを、「上司学」の権威が余すところなく解説する。
<目次>
第1章 部下はいかにして動くか
人間関係にセオリーはない
人間関係は、「縦」ではなく、「横」で見る
自分の評価は厳しく、部下の評価は甘く
第2章 部下の悩みといかに向き合うか
修羅場体験が「考える力」を養う
面談で部下の心を開く
士気低下の原因を特定する
第3章 難しい部下との向き合い方
部下の成長を絶対に諦めない
信頼口座に貯蓄する
正面の理、側面の情、背面の恐怖
第4章 部下とともに大きな成果を挙げるには
人を集めるのではなく、育てる
部下は生徒であり、教師である
組織は、ナンバー2で決まる
第5章 働き方改革と管理職のあり方
働き方とは、生き方である
重要度を見分ける目を持て
制度より風土、風土より上司
第6章 多様化する部下を動かす
「年上の部下」に尊敬の念を
女性が活躍できない会社に、未来はない
退職を願い出た部下は、引き止める
佐々木 常夫[ササキ ツネオ]
著・文・その他
内容説明
働き方改革が叫ばれる一方で、成果を厳しく問われるという、組織の中間管理職にとって受難の時代が到来している。そこではますます多様化する部下の力を十二分に発揮させることが、問題解決の重要な点である。部下の意欲を引き出すためのコミュニケーションの取り方や、組織の根幹となる「信頼と志」の重要性などを余すところなく解説する。
目次
第1章 部下はいかにして動くか
第2章 部下の悩みといかに向き合うか
第3章 難しい部下との向き合い方
第4章 部下とともに大きな成果を挙げるには
第5章 働き方改革と管理職のあり方
第6章 多様化する部下を動かす
著者等紹介
佐々木常夫[ササキツネオ]
1969年、東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男を含め3人の子どもを持つ。しばしば問題を起こす長男の世話、加えて肝臓病とうつ病を患った妻を抱え多難な家庭生活。一方、会社では大阪・東京と6度の転勤、破綻会社の再建やさまざまな事業改革など多忙を極め、そうした仕事にも全力で取り組む。2001年、東レ同期トップで取締役となり、03年より東レ経営研究所社長となる。10年、(株)佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表。何度かの事業改革の実行や3代の社長に仕えた経験から独特の経営観をもち、現在、経営者育成プログラムの講師などを務める。社外業務としては内閣府の男女共同参画会議議員、大阪大学客員教授などの公職を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とみやん📖
ケン五
aochama
たかひー
kaz