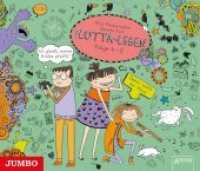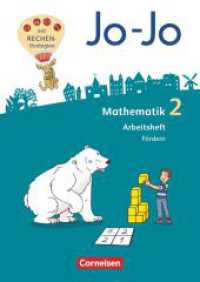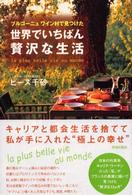出版社内容情報
脳科学・ロボット工学者で幸福学の第一人者による実用的日本人論。日本が持つ幸福の源泉や多様性を受容する日本人の特徴などを分析し、誰もが幸せになれる日本型システム、共生社会の未来について考察する。
【著者紹介】
前野隆司(まえの・たかし)1962年生まれ。東京工業大学卒、同大学院修士課程修了。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長・教授。博士(工学)。幸福学の第一人者。主な著書に『幸せのメカニズム』『脳はなぜ「心」をつくったのか』ほか。
内容説明
脳科学・ロボット工学者で幸福学の第一人者による実用的日本人論。西洋と東洋を俯瞰しながら、多様性を受容する日本人の特徴などを分析し、誰もが幸せになれる日本型システム、共生社会の未来について考察する。
目次
第1章 これまでの日本論・日本人論・日本文化論
第2章 日本人の十の特徴とは?
第3章 日本は中心に無がある国
第4章 東洋と西洋の二千五百年を俯瞰する
第5章 世界の中の日本の二千年
第6章 日本人の十の特徴は良い特徴である
第7章 日本人は女性的か、男性的か?
第8章 外国人に「日本人とは」を伝える方法
第9章 日本はどれくらい特殊なのか?
第10章 全体が調和し、共生する未来社会
第11章 繁栄の時代がやって来る
著者等紹介
前野隆司[マエノタカシ]
1962年、山口県生まれ。東京工業大学卒、同大学院修士課程修了。キヤノン入社後、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、ハーバード大学客員教授、慶應義塾大学理工学部教授等を経て、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長・教授。博士(工学)。専門は、システムデザイン・マネジメント、ロボティクス、幸福学、感動学、協創学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kikuyo
デビっちん
茶幸才斎
いまちゃん
Hayek