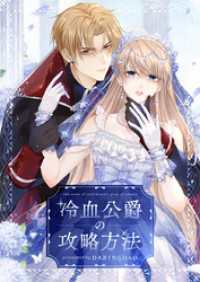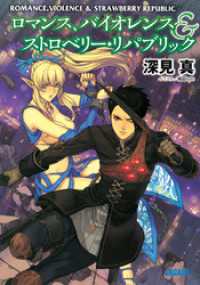出版社内容情報
看取りの現場での後悔を、わずかでも少なくするために。
死に向かう人が肉体的にどういう過程をたどるか。
延命治療にはどういうものがあるのか。
逝く人の心に寄り添うにはどういう対話をすればいいのか。
看取る人の心が折れないためには、周囲のどういうサポートが必要か。
逝く人、看取る人、その近くにいる第三者の視点から、
相手を傷つけず、心に寄り添う対話をするにはどうすればいいのか──。
緩和ケアの最前線にいる現役医師による、終末医療の最新情報も掲載
内容説明
看取りの現場での後悔を、わずかでも少なくするために。死に向かう人が肉体的にどういう過程をたどるか。延命治療にはどういうものがあるのか。逝く人の心に寄り添うにはどういう対話をすればいいのか。看取る人の心が折れないためには、周囲のどういうサポートが必要か。逝く人、看取る人、その近くにいる第三者の視点から、相手を傷つけず、心に寄り添う対話をするにはどうすればいいのか―。終末医療の最新情報も掲載。
目次
序章 これからは、自宅で家族を看取る時代
第1章 最新の終末医療がもたらしたもの
第2章 体が発する「サイン」たち
第3章 看取りの心得
第4章 「最期の対話」実例集
第5章 “看取る人”を支える対話「9つの約束」
終章 「話す」ことは「放す」こと
著者等紹介
玉置妙憂[タマオキミョウユウ]
看護師・僧侶・スピリチュアルケア師・ケアマネージャー・看護教員。東京都中野区生まれ。専修大学法学部卒業。高野山真言宗にて修行を積み僧侶となる。現在は「非営利一般社団法人大慈学苑」を設立し、終末期からひきこもり、不登校、子育て、希死念慮、自死ご遺族まで幅広く対象としたスピリチュアルケア活動を実施している。また、子世代が“親の介護と看取り”について学ぶ「養老指南塾」や、看護師、ケアマネジャー、介護士、僧侶をはじめスピリチュアルケアに興味のある人が学ぶ「訪問スピリチュアルケア専門講座」等を開催。さらに、講演会やシンポジウムなど幅広く活動している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
yumiha
たまきら
okatake