内容説明
作者が生まれた町、そして愛してやまない町、新潟県の高田をモデルにした作品集です。「坂のある風景」から「海のある風景」まで8章、合わせて45編の物語と小品。「乳母車」「あの坂をのぼれば」「月夜のバス」「風船売りのお祭り」など、教科書関連図書にも登場する渋い宝石箱のような一冊です。赤い鳥文学賞受賞作。小学上級以上向。
著者等紹介
杉みき子[スギミキコ]
1930年、新潟県高田市(現在、上越市)生まれ。長野女専国語科卒業。1957年、日本児童文学者協会新人賞を受賞。日本児童文学者協会会員。作品に『小さな雪の町の物語』(小学館文学賞)など。『小さな町の風景』で赤い鳥文学賞受賞
佐藤忠良[サトウチュウリョウ]
1912年、宮城県生まれ。東京美術学校彫刻科卒業。日本人の顔の連作で高村光太郎賞を受賞。新制作協会会員。1981年フランス国立ロダン美術館で個展開催。アカデミー・デ・ボザール会員。主な作品にサンケイ児童出版文化賞大賞の『ゆきむすめ』『おおきなかぶ』など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
111
小さな町で起こる小さな奇跡を連作の形で描く児童文学。ファンタジックな要素が、平凡な地方都市の生活の描写に無理なく溶け込んでいるところが素晴らしい。坂や木、電柱といったありふれたものの中にも魔法が潜んでいるのだ。電柱たちが電線で手をつないで「花いちもんめ」をする「雪の夜ばなし」が私のベスト。宮沢賢治の「月夜のでんしんばしら」を思わせる幻想的な物語。2014/05/26
ぶんこ
49
著者の故郷の町の光景を題材にした、少し長めの詩のような短編集。文章が美しく、リズムがあって、ホクホクと心に沁みてくるようでした。最も好きだったのは「遠い山脈」で、新聞配達の少年と、元(かなり昔の事ですが)新聞配達少年だったおじいさんとの素敵なお話。岩かげのわずかな隙間から、白い神のような遠い山が浮かび上がり、朝陽に輝いている。白い雪山に朝陽が赤く輝く様が見えるようでした。他の作品も短い中にも、フッと心温まる話が多く、ぬるめの温泉にのんびりつかっているような読後感です。2016/07/29
ワッピー
43
この小さな町の坂、商店、塔、木、電柱、鳥、橋、海というテーマで切り取られた物語たちは、心のつながりを描くもの、美しい風景を描くもの、不思議な現象を描くもの、樹霊を思わせる話、白鳥を愛した老人の最後とさまざまですが、全編に詩情を感じられるすばらしい作品でした。この小さな町のモデルは現在の上越市の一部となった高田の由で、これまで訪れたこともないのに、とても懐かしく感じました。著者が書いているように、こうした物語はどの町にもあるのだとしたら、自分の町の物語を、鳥や木や建物から聞けるようになりたいです。おススメ!2022/11/01
アナクマ
31
童話作家の小品集。故郷・上越高田をモチーフに虚実まじえた抒情的な掌編。 ”長めの日記“ の残し方に長いこと腐心しているのですが、ヒントが児童文学にあった感じ。本書のように、事実と空想と幾許かの真理を、ザクザクと歯切れよく朝のサラダのように刻めばいいのかもと。◉閑話休題、書評から外れました。3羽の風見鶏がそろって見つめているものや、新聞少年が受け継いだことなど。短さゆえに印象に残るエピソードとか、現実の断片(岸政彦)が、長い人生を支え得ること。そんなある種の希望を想起させられた一冊。→2022/12/17
ゆう
8
フォロワーさまより教えていただいた本。ふわりと優しい雰囲気なのに、何処と無く幻想的な、かと思えば不思議な雰囲気であったり、寂しく感じるものがあったり。読んでいてふっとその情景が頭に浮かび優しい気持ちになれる本。小学生向けなのか、ひらがなまじりの表現も個人的には好みでした。2017/09/07
-
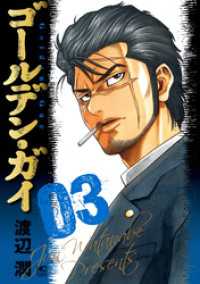
- 電子書籍
- ゴールデン・ガイ 3




