出版社内容情報
太夫、三味線、人形遣いの芸と、舞台を支える職人たちがつちかってきた技を図版とともに紹介。文楽への興味につながる1冊。
岩崎和子[イワサキカズコ]
内容説明
文楽は三三〇年ほど前に、江戸時代の大阪で生まれました。太夫が語り、三味線が演奏する義太夫節と、三人の人形遣いによって演じられます。このような形式の人形芝居は、世界でもめずらしい芸能だといわれています。太夫、三味線、人形遣いの芸と、舞台を支える職人たちがつちかってきた技を図版とともに紹介。文楽への興味につながる一冊。小学校中学年から。
目次
基礎知識編(文楽ってどういうものかな?;舞台を見てみよう;上演中の舞台を見てみよう ほか)
支える人たち編(衣裳―人形に合わせて特別仕立て;首係―公演に合わせてぬりかえる;床山―役それぞれの髪を結いあげる ほか)
資料編(文楽を楽しもう;文楽が見られる主な劇場;伝統芸能が調べられる場所/伝統芸能が調べられる本 ほか)
著者等紹介
岩崎和子[イワサキカズコ]
1949年、東京生まれ。元東京成徳大学人文学部日本伝統文化学科教授。文部省・文部科学省教科書調査官を経て、お茶の水女子大学、立教大学、駒沢女子大学などで非常勤講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びぃごろ
16
ふり仮名付きで小学生~OK。基本的なことも専門用語の確認もできます。床山さんのかつらの作り方や、お囃子さんではカエルの鳴き声は貝殻をこすり合わせるとか、擬音笛は17種もあるなど知らなかった裏話も。千歳太夫の手書き床本☆.☆富助さんの爪の糸道と小指のタコに目を見張る。2017/05/07
花林糖
10
(図書館本)330年ほど前に大阪で生まれた文楽を、写真とイラストでわかり易く解説した絵本。首(かしら・人形の頭部分)・衣装・首係(かしらがかり)・床山・小道具についてが特に楽しく読めた。巻末の「ミニミニ用語基礎知識」が有難い。2017/04/29
chiaki
8
6年国語「『鳥獣戯画』を読む」、日本の伝統文化提供資料。2020/10/02
Yoshihiro Yamamoto
3
A 先日、上野へ行った時に見つけた国立国会図書館「国際子ども図書館」。中へ入って、小学生までを対象とした部屋に入ってみたら、難しいことをビジュアルを多用して易しく書いてある本」をたくさん見つけた。あらゆることの基礎基本が短時間で学べる良い方法を見つけた!早速地元の図書館をみてみたら幸い所蔵してあったので、まずは自分が一番関心のある古典芸能系の本を借りてきた。やはり、自分が知らないことで、基本的なこと(主に言葉の意味)が数多く書かれており、大いに参考になった。こうしたことを小学生が知っているとは、侮れない。2018/02/20
piro5
1
主遣い、足遣い、左遣いの3人が人形を使うのか。。とか勉強になるなぁー。舞台や人形の構造も分かりやすく解説されてる。このシリーズは面白い。2019/02/23



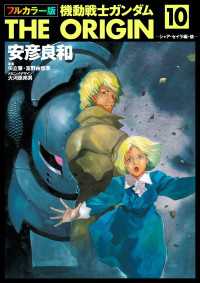

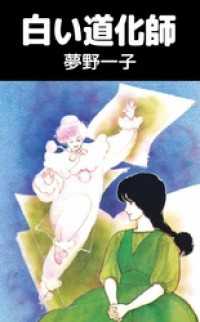
![ポルトガル語基本単語2000 - 聴いて,話すための [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48761/487615659X.jpg)


