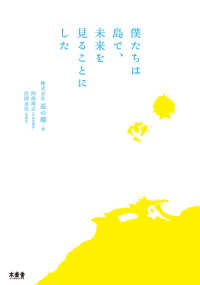出版社内容情報
2部構成で、歌舞伎が楽しく見られる基礎知識と、舞台の裏ではたらく人たちの仕事ぶりをわかりやすく解説したシリーズ。
矢内賢二[ヤナイケンジ]
内容説明
歌舞伎を楽しむ基本の事項と、大道具 小道具 衣装、かつらなど、職人たちの仕事と技を紹介。実際に歌舞伎の舞台が見たくなる。小学校中学年から。
目次
基礎知識編(歌舞伎ってどういうものかな?;歌舞伎の舞台を見てみよう;秘密がいっぱい、舞台のしかけ ほか)
支える人たち編(大道具―華やかな舞台をつくりだす職人集団;小道具―より本物らしく魅せる小道具;かつら―役に入っていくための一ミリの工夫 ほか)
資料編(歌舞伎を楽しもう;歌舞伎が見られる主な劇場;伝統芸能が調べられる場所/伝統芸能が調べられる本 ほか)
著者等紹介
矢内賢二[ヤナイケンジ]
1970年、徳島県生まれ。日本芸術文化振興会(国立劇場)勤務などを経て、国際基督教大学准教授。幕末から明治期の歌舞伎を中心とする日本芸能史・文化史を研究。主な著書に『明治キワモノ歌舞伎空飛ぶ五代目菊五郎』(白水社、第31回サントリー学芸賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- パクスムーダン・ペク先生【タテヨミ】第…
-

- 電子書籍
- あんた私のことを好きだったの?【タテヨ…