出版社内容情報
昆虫は、あしが6本。このことは学校などでしっかり教わったはずです。
その一方、昆虫ではない虫は、あしがたくさんある、ということもなんとなく知っているでしょう?
クモは、あしが8本。ではムカデは、あしが何本? ヤスデは? サソリは? ダンゴムシは? ところでそれぞれ、いったい何のなかま? クモ以外になると、とたんにわからなくなるのは、昆虫ではない「あしの多い虫」は、いつも昆虫図鑑の最後にちょこっと紹介されるだけだからかもしれません……。
この本は世界初、昆虫ではない「あしの多い虫」が主役の図鑑。この図鑑では、4つのグループの中のさらに細かい分類にそって、日本の代表種を最低1種、計約90種を中心に、コラムでは海外にすむものも紹介し、総数として計約100種を掲載しています。写真は、生態写真を基本に、体のつくりがよくわかる白バック写真も加え、生息環境や探す手がかり、育ち方の写真なども掲載します。また、昆虫と昆虫ではない虫をさらに包括する「節足動物」の説明や、古代にいた巨大ヤスデの話題、クマムシやカギムシなどの節足動物に近い動物、古代の三葉虫やアノマノカリスなどについても、コラムで楽しく取りあげます。
内容説明
昆虫ではない虫、つまり、あしが8本以上ある虫だけを100種近く紹介する、世界初、あしの多い虫図鑑。あしの多い虫は、あしの数や体の形もいろいろ。「なにが、なんのなかまなの?」と思う人が多いかもしれません。でも、整理すると、分類は意外にシンプル。見つけやすいのは、ムカデ綱、ヤスデ綱、クモ綱、陸生甲殻類の4グループです。各グループの体のつくりなどの特徴とよく見られる種を、あしの数も手がかりにして、わかりやすく説明します。
目次
ムカデ綱(ゲジ;イッスンムカデ ほか)
ヤスデ綱(ハイイロフサヤスデ;ヤマトタマヤスデ ほか)
クモ綱(ヤエヤマサソリ;アマミサソリモドキ ほか)
陸生甲殼類(オカダンゴムシ;トウキョウコシビロダンゴムシ ほか)
著者等紹介
小野展嗣[オノヒロツグ]
1954年、神奈川県川崎市生まれ。小学生のころからカエルやいろいろな虫と親しむ。学習院大学法学部卒業後、ドイツのマインツ大学生物学部に留学(中退)。理学博士(京都大学)。国立科学博物館(研究主幹・九州大学大学院客員教授兼任)を2019年に定年退職し、現在は名誉研究員。神奈川大学非常勤講師。日本動物学会会員。専門分野は動物系統分類学、昆虫学、とくにクモ類。ベトナム、タイ、ミャンマーなどを踏査。国際クモ学会賞受賞(2010年)
鈴木知之[スズキトモユキ]
1963年、埼玉県越谷市生まれ。昆虫写真家。國學院大學卒業。青年海外協力隊としてパプア・ニューギニアに赴任し、アレクサンドラトリバネアゲハの保護活動を行う。帰国後、昆虫写真家として、日本だけでなく、東南アジアやオーストラリアの熱帯雨林でも撮影(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
たまきら
アナクマ
紫陽花と雨
FOTD
-

- 電子書籍
- 推定悪役令嬢は国一番のブサイクに嫁がさ…
-
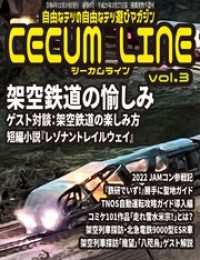
- 電子書籍
- エビコー鉄研部誌:シーカムラインvol…
-
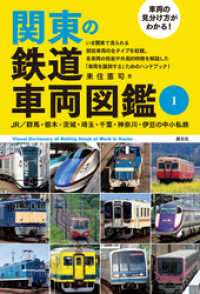
- 電子書籍
- 車両の見分け方がわかる! 関東の鉄道車…
-
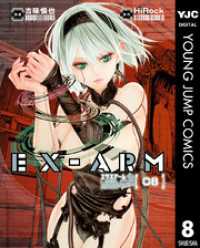
- 電子書籍
- EX-ARM エクスアーム 8 ヤング…




