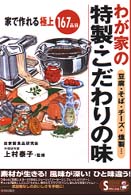出版社内容情報
突き詰めて考えれば、人間は「死」を食べているとも言えます。動物の「死」を観察することによって、人類の飽食や命の大切さを考えます。 小学校中学年から
著者等紹介
宮崎学[ミヤザキマナブ]
1949年、長野県に生まれる。精密機械会社勤務を経て、1972年、独学でプロ写真家として独立。『けもの道』『鷲と鷹』で動物写真の世界に新風を巻き起こす。現在、「自然と人間」をテーマに、社会的視点に立った「自然界の報道写真家」として日本全国を舞台に活躍中。1978年『ふくろう』で第1回絵本にっぽん大賞。1982年『鷲と鷹』で日本写真協会新人賞。1990年『フクロウ』で第9回土門拳賞。1995年『死』で日本写真協会年度賞、『アニマル黙示録』で講談社出版文化賞受賞。現在、長野県駒ヶ根市在住。日本写真家協会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
空猫
38
読メで知り。定点カメラで動物(魚)達の死後の様子を写真に納めたモノ。これは子供向けの本だ。『九相図』は写生だし、ヒトの死体を扱う『死体農場』の写真はさすがにモノクロだけれど、こちらはフルカラー。ハクビシンはウ○¨を食べるのか(|||´Д`)。生死が家(身近)でなく病院で済まされてしまう上、すこしの怪我で大騒ぎする現代日本では衝撃的だ。けれど、それほど死、自然から遠ざかっているのだと気付く。生きていくということは、他の命をいただく事だと忘れてはいけないのだ。2021/09/30
たまきら
32
ううむ、なんと質の高い本が絵本コーナーにはあるんだろうなあ。人間が作り出す様々なタブー・禁忌・制限。そしてそこから生まれる罪悪感。それが人間の面白さだけど、「生き残り、子孫を残す」という時に寄り添う生物の掟こそ唯一無二なんだよなあ…と娘を横にしつつ考え込んでしまった。2017/08/09
兎乃
30
『九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術史 (角川選書)』とセットで読む。直視できるのは 写真に死臭が伴わないからか、あるいは自分が野生として失格 もしくは合格だからか、福島で逃げ去ることができなかった牛や豚の“九相図”を見たからか。2015/08/06
スノーマン
30
正直、目をそらしたくなる写真もあるけど、こういうことはなかなか教えてもらえない。残酷に思えても、そんな私たちも死を食べている。息子は夢中で文や絵を書き写したりしてたので、子供は大人が思うより『死』や『死体』に興味があり、自分と何が違うのか、死ぬとどうなるのかを純粋に知りたいのかな。でも正直、死体の写真は怖いよ〜。2014/07/02
ピンガペンギン
21
キツネの死の「時間」。秋に死んで、半年後の冬に骨とわずかの毛皮になるまでがロボットカメラで撮影されている。現代の文明の中では生きている時間が称揚(?)されているというか、死は、どうしても不吉で、なるべく見ない、覆い隠されたもので、もう若くないのに死について考えることは少ない。この本で写真を見ると、死はただの自然現象で、食物連鎖の一環であることがわかる。日本は昔は土葬が多かったんですよね。現在は人口が増えすぎて火葬率99.8%ですが。土葬ならこの本にあるように自然にゆっくり還っていくのか…とも思った。2025/09/01


![モノクローム・ファクター 〈5〉 Blade comics [特装版コミック] (初回限定版)](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)