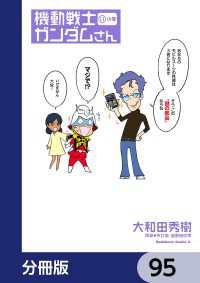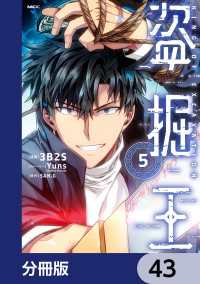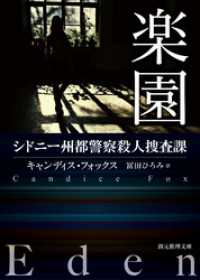出版社内容情報
江戸時代の子どもたちは、どのように毎日遊んでいたのでしょうか?江戸の子どもの1年を行事と遊びを中心に見る絵本。
内容説明
江戸時代へようこそ。お正月には凧あげ、端午の節句には菖蒲打ち、七夕には回り灯篭…。江戸時代の子どもたちのあそびを月ごとの行事といっしょにおいかけてみましょう。小学校低学年から。
著者等紹介
菊地ひと美[キクチヒトミ]
日本画家、江戸民俗学研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Squirrel
13
見開きでひと月、合間に遊びの種類紹介など。あれもこれも江戸時代から続いてたんだぁ、すごいなぁ。柔らかい絵と色彩で心地よいです。ぶりぶりっていうのはお初でした。なぜぶりぶりと呼ぶのか知りたい。2014/06/30
千尋
13
江戸時代の行事と子どもたちが遊んでいた遊びを12ヶ月ごとに綺麗なイラストで解りやすく紹介しています*おままごとやあやとりなど、江戸時代から伝わっている遊びを知る事が出来ました*2012/07/29
猪子
8
菊地ひと美さんが描かれる江戸の子どもは生き生きしていて可愛い。江戸時代は今みたいに多種多様なおもちゃがあるわけじゃないけど、みんな工夫して楽しそうに遊んでていいな。私は駕籠かきごっこがしてる子たちが好き。2018/05/07
ぴよぴよ
7
なかなかのおもしろさ。お正月に町へやってくる、万歳(まんざい)という人たち。(二人組で家いえをまわり、お祝いの言葉や、おもしろい歌や踊りを演じる。)もしや漫才の語源?2012/05/29
遠い日
5
江戸時代の子どもの遊びは、行事や季節と今よりずっと密接に関連している。現代まで連綿と続く変わらぬ遊びには、やっぱり単純で楽しい要素があるのだと思う。反対に「初午」や「歌舞伎ごっこ」など、当時の文化ならではの遊びに目をひかれる。2014/04/28