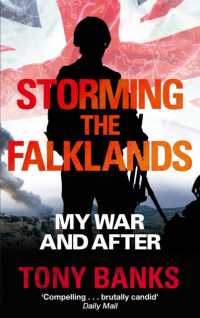内容説明
バリ島の棚田を歩く。はるかな山にむかってつらなる美しい田んぼ。それは自然への感謝がつくりだした神様の階段。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
78
数多くの自然写真を撮っている著者。インドネシア・バリ島の棚田が舞台だ。そこは常に人と動植物、田んぼ作りの担い手でもある家畜そして神と共存している。山に住んでいる神々の通り道とされているのがその棚田だ。そして棚田を「神様の階段」と呼ぶ。昔の日本の農業もバリ島と同じような形で行われていと所も多いのではないか。近年大掛かりな機械化により神との共存も薄れたようの思う。朝夕の田んぼを照らす太陽がとても美しかった。図書館本。2016/09/13
モリー
70
私の身近な美しい風景は、急速に失われつつあります。なぜだろう?ととぎどき考えます。本書はバリ島の美しい棚田を紹介しています。日本人が忘れつつある土地に対する感謝の心が美しい風景を創り出し、そして、守っているのですね。以下、引用。「バリ島の人たちにとって、お米をつくることは、神様が住む神聖な森に近づくこと。人々は、森が、水を育み、自分たちを生かしてくれることをしっている。土地に対する感謝の心が、美しい風景をまもりつづけている。」2020/03/01
明るい表通りで🎶
46
バリ島にイキたくなった(^^) 人々にとって、田んぼは、山の神のすむアグン山へ続く道。山に向かってかさなる棚田は〈神様の階段〉。機械化されてない米作り。日本の明治大正時代だろうか。2025/02/07
アナクマ
38
里山写真家がバリ島の棚田を行く。「息をのむほど美しい」しなやかな曲線のあぜに縁取られた田んぼの水面群に、農作業と生き物と祈りが響きあう。◉どこか違和感を感じた序盤の空撮写真の理由は → 稲株が残る薄茶の刈田や、起こしたばかりの黒々とした田面、早苗の田、青葉がモリモリと繁る水田などが一枚の写真に仲よく収まっている不思議。なぜなら「一年を通じて気温が高いので、きまった時期に田植えをする必要がない。だから、それぞれの田んぼで稲刈りの時期もちがっているのだ」。なんたるカルチャーギャップ。10年刊。→2024/02/18
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
15
インドネシアのバリ島で、一番高いアグン山に向かって連なる棚田の美しさ。日本では少なくなった風景の1つ。2023/04/20