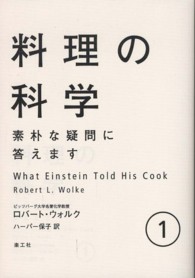出版社内容情報
ワタネ・マンとは「わたしの国」という意味。22年間の取材で出会った、いきいきとした子どもたちの写真集。カラー写真73点収録。 子どもから大人まで
内容説明
写真家・長倉洋海が22年間撮りつづけてきたアフガニスタンの子どもたち。咲きみだれる花々や緑豊かな土地など、ニュース映像では見られない色あざやかな大地にくらす子どもたちの日常をきりとる。アメリカによる2001年の空爆後の写真も収録。
著者等紹介
長倉洋海[ナガクラヒロミ]
1952年北海道釧路市生まれ。写真家。1980年よりアフリカ、中東、中南米、東南アジアなど世界の紛争地を訪れ、そこに生きる人々を見つめてきた。アフガニスタンは1980年から取材を続けている。写真展「アフガンの大地を生きる」(富士フォトサロン/東京、札幌、大阪、名古屋などを巡回)で、2002年日本写真協会年度賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
272
主として1999年~2001年頃のアフガニスタンの子どもたちの写真集。撮影地の多くはタリバーンの勢力の埒外にあったパンシール渓谷の集落。表紙はヒンズークシ山脈の麓だろう。どの写真の被写体になった子どもも実に生き生きとしかも、生活感まで伴っていて、確かなリアルさに裏打ちされている。とりわけ働く子どもたちの姿がいい。アフガニスタンの平均寿命はマラウィに次いで、世界で最下位から2番目。戦乱とそれに伴う貧困等で若くして命を落とすのだろう。ここにいる子どもたちの生の軌跡に打たれるとともに、平和を希求してやまない。2017/05/22
とよぽん
17
サブタイトル「わたしの国アフガニスタン」。子供たちの真っすぐな視線、澄んだ瞳が、祖国への誇りを表すことに心打たれる。子供たちが家族や誰かのために「はたらく(はたを楽にする)」様子がたくさん載っていた。2018/07/27
ヒラP@ehon.gohon
16
紛争の続いたアフガニスタンで、「ここがわたしの国だ」と生きている人のたくましさに感じ入りました。 長倉洋海さんの切り取ったアフガニスタンは、そこに生きる人びとの生きざまそのものでした。 決して裕福ではない彼らは、だからと言って絶望的ではありません。 懸命に生きる姿に、誇りのようなものも感じました。2019/02/08
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
16
ワタネ・マンとはアフガニスタンの言葉で、私の国という意味です。アフガニスタンというと、戦火に苦しめられている国というイメージがありましたが、長倉洋海さんの撮る子どもたちの表情からはそんな影が見えてきません。子どもたちは夢を語り、誇りをもって暮らしているのがわかります。2018/10/05
ぽんくまそ
12
写真集。国は違えど民は違えど、わらしこはめんこい。わしらの唯一の目的にして希望、可能性、宝じゃよ。you tubeで見つけた動画で、てっきり「世界のこどもたち」かと思ったら「アフガニスタンのこどもたち」で、その衣装・人種の不統一ぶりに、さすがシルクロードのど真ん中だけのことはあると驚いたことがある。これは、そんな国へ東のはて日本から来たおじさんに見せてくれた彼らの「当たり前」がこの本だ。アフガニスタンが執拗な破壊にさらされてきた理由は、希望にいっぱいな彼らの地を、サタンがひがんだのではないかとすら考えた。2015/09/15