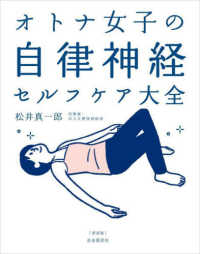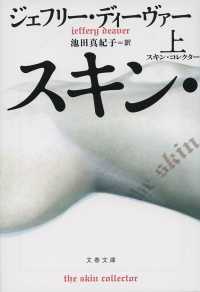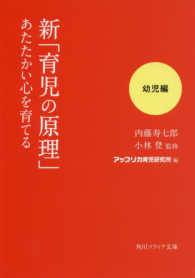内容説明
もし、ほんとうにウスタビガになれたら、いかほどうれしいであろう。ウスタビガの生命それ自体となれたら、どんな感覚がするだろう―前作『虫屋の虫めがね』に続く第二弾。虫とのつきあい、虫仲間との交遊を軸に、その会話には、自然科学への好奇心とユーモアが絶えることがない。
目次
ある昆虫愛好家のひとりごと
モンキアゲハ
エビガラスズメの幼虫とサツマイモ畑のババア
キアゲハとパセリ
オオスカシバ
やはりオオムラサキは…
青羽せせり
柊の幼虫
青い勲章の綬
しゃちほこ蛾と銀紋雀もどき
イシガケチョウ
山繭蛾のあたらしい産卵場所
万華鏡
在宅採集
脳のほうはだいじょうぶか
著者等紹介
田川研[タガワケン]
1948年広島県福山生まれ。上智大学フランス語学科卒。塾・専門学校などで、英語とフランス語を教えるかたわら、少年時代からの昆虫趣味を捨てきれず、現在にいたる。虫屋仲間とともに、「びんご昆虫談話会」をつくり、その会員でもある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rinpei
1
著者の住む福山市、私も20代に計7年住んでいた。虫を追いかけていたのは少年期と40代の頃で、今でも細々と興味をつないでいるが、当時はある哺乳類の雌を追い回すのに夢中で、昆虫への興味は失せていた。さて苦労の末その種の雌を一頭捕獲し、神戸まで連れ帰り、現在に至っている。ツマキチョウのように清楚で美しかった雌の容貌はカトカラの前翅のようにくすんでしまい、細く締まった躯幹はキイロスズメの終齢幼虫の如くぶよぶよとなった。が、クロメンガタスズメの幼虫を手に乗せ愛でることのできる私なら耐えられる。…。はず。…。だと思う2015/01/16
まんまるプーさん
0
蝶蛾屋ケンさんの採集記
paxomnibus
0
2006年出版なのに、随分古臭い印象の本。昭和の頃に流行った北杜夫等の随筆のようで、さらに古くは明治の文豪、夏目漱石の影響もありそう。著者が1948生まれなので無理もないのだろうが、身体に染みついている「昔ながらの教育」の匂いがぷんぷんする。それは空気のように当たり前に「女性を男性より下に見る視線」。妻達や母達を語る時のステレオタイプ化。ご本人に女性蔑視をしてるつもりは毛頭ないのだろうが、「男は女より上」とごく自然に思い込んでいるのだ。15年前なら楽しめたかもしれないが、時代はすでに変わってしまったのだ。2019/05/02