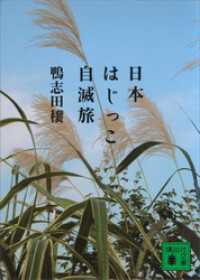出版社内容情報
なぜ日本の賃金は上がらないのか──。日本型制度の「決め方」「上げ方」「支え方」の仕組みを、歴史の変遷から丁寧に紐解いて分析し、徹底検証。近年の大きな政策課題となっている問題について、今後の議論のための基礎知識を詰め込んだ必携の書。
内容説明
上げなくても上がるから上げないので上がらない日本の賃金―その仕組みとは。日本の賃金制度は、どのように確立されてきたのか。ベースアップや定期昇給とは何か?そもそも賃上げなのか?今日の大きな政策課題となっている「賃金」について、「決め方」「上げ方」「支え方」の側面から徹底検証。今後の在り方を議論するための、基礎知識を詰め込んだ必携の書。
目次
序章 雇用システム論の基礎の基礎
第1部 賃金の決め方(戦前期の賃金制度;戦時期の賃金制度;戦後期の賃金制度;高度成長期の賃金制度;安定成長期の賃金制度;低成長期の賃金制度)
第2部 賃金の上げ方(船員という例外;「ベースアップ」の誕生;ベースアップに対抗する「定期昇給」の登場;春闘の展開と生産性基準原理;企業主義時代の賃金;ベアロゼと定昇堅持の時代;官製春闘の時代)
第3部 賃金の支え方(最低賃金制の確立;最低賃金制の展開;最低賃金類似の諸制度)
終章 なぜ日本の賃金は上がらないのか
著者等紹介
濱口桂一郎[ハマグチケイイチロウ]
1958年大阪府生まれ。労働政策研究・研修機構労働政策研究所長。東京大学法学部卒業。労働省、欧州連合日本政府代表部一等書記官、衆議院調査局厚生労働調査室次席調査員、東京大学客員教授、政策研究大学院大学教授を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
よっち
ATS
Francis
ザビ