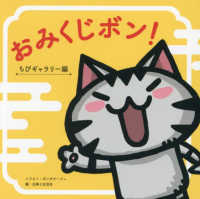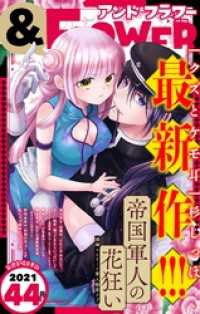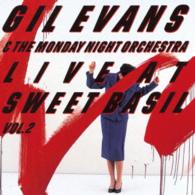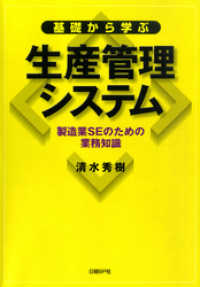出版社内容情報
発達障害は本当に「障害」なのか? 学校、会社や人間関係に困難を感じる人々の事例から、周囲が変わったことで「障害」でなくなったケースを紹介。当事者と家族の生きづらさをなくす新しい捉え方、接し方を探る。朝日新聞大反響連載を書籍化。
内容説明
当事者の生きづらさに寄り添う新しい捉え方、接し方とは?発達障害の特性から、学校生活、仕事、人間関係に苦悩を感じる人は数多く存在する。しかし、その原因は当人だけによるものなのか?周囲の環境が変わることで、困難が軽減した事例を紹介する。「朝日新聞」大反響連載、待望の書籍化!
目次
第1章 私は「できない」女?―ADHD女性の生きづらさ(私は「人間失格?」;「お前はくず」結婚は地獄の一丁目;モラハラ夫と別れて……;自分の「トリセツ」)
第2章 「ツレ」が発達障害―ふりまわされる、でも愛している(義母のメールで知った妻の発達障害;雑談できない夫と家族の再生)
第3章 発達「障害」でなくなる日(変わるべきは親?;配慮しない学校、動いた母;大学中退―「おれ、どうする?」からの逆転;得意分野を生かして「再構築」)
第4章 合理的配慮とは―企業の現状と課題(合理的配慮とは何か;会社はどうすればよいか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
リリー・ラッシュ
21
アメリカの診断基準では症状があることに加えて「症状によって、日常生活などに明らかな障害を引き起こしていること」という条件が明記されているとのこと。『つまり特性があるだけでは疾患にならず、周囲との関係性のなかではじめて、発達障害は「障害」になる』と。「合理的配慮」についてとても分かりやすく書かれている。『何が本質かを考えていくと、思った以上に本質ではない部分へのこだわりが隠れていたりします。そこを変更·調整していけば、誰にとっても生きやすくなりますよね。』障害法が専門の川島さんの言葉、忘れないでおきたい。2024/05/12
呼戯人
18
新聞連載をまとめた本。発達障がいを個性の一つとして捉え、その個性が生きやすいように環境調整するという趣旨が一貫している。ニトリの社長の似鳥さんがADHDだったというインタビューがあり、苦労してあのような巨大な家具屋さんを作った話に興味を惹かれた。ただ、ASDやADHDの本質に迫り、本人や家族や医療や社会制度がどのように努力して行けば良いのか、包括的なヴィジョンはなかった。しかし、日本の同調圧力や差別主義などの風潮は発達障がいの人々を差別するだろうし、合理的配慮の要請を法律で定めたところで道遠しの感あり。2024/05/11
Asakura Arata
6
発達障害の特性を持つ方と接することは多いのだが、この人「障害」じゃないよなあと思うことがほとんど。特性というものは、いかに生かすことがナンボだと思うし。大体、利点になることもある障害特性って何よ。「〜症」もイマイチだし、ネーミング変えた方が良いよなあ。あとがきにも記してあったが、ある意味「同調圧力」でもあるよな。普通にしろとか、普通じゃないと変とか。 俳句のTV録画見ながらこれを打ち込んでいたら、山崎ナオコーラが出ていて、このサイトの検索候補に彼女のエッセイ「母ではなくて、親になる」がアップされている。2023/11/19
読書熊
6
障害と共に生きるとは、どういうことか。ヒントになる2023/11/18
ひつまぶし
5
大人の発達障害について、当事者による体験談や対処法の解説ではなく、医師による解説でもなく、第三者が取材して書いた本というのは珍しいのではないか。ニトリの社長の記事への反響から発達障害をテーマとした企画を立て、読者からの反応がまた連載の内容を豊かにしていったというのは新聞の可能性を感じさせる話でもあった。大人の発達障害について具体的な事例がもっと集積されていけば、どんどん理解も進むのではないか。発達障害を持つ人の家族の話もあり、相互行為を視野に入れて構成したところも本書の特長だと思う。文章も読みやすかった。2023/12/03