出版社内容情報
日本人の旅行好きは江戸時代から始まった! 農民も町人も男も女も、こぞって観光旅行を楽しんだ。その知られざる実態と背景を詳述。土産物好きのワケ、関所通過の裏技、飲食・名所巡りのお値段、漬物石まで運んだ大名の「団体旅行」の苦心談……。 誰かに話したくなる一冊!
内容説明
「旅行ガイドブック」を開いて、心うきうきと「買い物は何を?芝居とのパッケージツアーはどう?」これは江戸時代の庶民の姿―。江戸中期、元禄年間から一大旅行ブームがわき起こった。成田へ伊勢へ善光寺へ、熱海・箱根の温泉へと庶民男女が繰り出した。武士や公家、大名、将軍は―かなり可哀そう。現代人もナットクの旅行エピソードと、その背景を解き明かす。
目次
第1章 庶民の旅の表と裏
第2章 買い物、芝居―したたかな女性の旅
第3章 大江戸、人気観光地となる
第4章 大名の「団体旅行」は七難八苦
第5章 乱暴極まりない武士・公家の旅
第6章 自粛を求められた将軍の旅
第7章 外交使節、江戸へ行く
著者等紹介
安藤優一郎[アンドウユウイチロウ]
1965年、千葉県生まれ。歴史家。文学博士(早稲田大学)。早稲田大学教育学部卒業。同大学院文学研究科博士後期課程満期退学。主に江戸をテーマとして執筆・講演活動を展開。「JR東日本・大人の休日倶楽部」などの講師を務める。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
245
日本人の旅好きDNAの原点を見た。観光好きになる基本は、江戸時代にできていたんですね。旅行代理店、ガイドさん、旅館組合、旅行ガイドブック、パッケージツアー、神社仏閣・温泉巡り、江戸の人気観光地化など、現代に通じる、ご先祖様たちの旅行熱が面白おかしく紹介されています。ちなみに江戸中期の東海道での一泊二食付基準宿泊費は2700~7500円。Go to Travelみたいなのはあったのかな?2022/01/09
パトラッシュ
104
日本人が初めて楽しむために旅行できるようになった江戸時代、その実態はどのようなものだったのかをまとめた1冊。伊勢や成田などの寺社参詣をはじめ買い物に芝居見物、江戸観光から大名行列まで当時のあらゆる旅の裏側は興味深い。宿屋の集客合戦が過熱して騒動になったり、女性も逞しく長旅に出ていた姿は現代にも通じるし、貧乏公家が公用旅行で財産を築く話は落語のようだ。御茶壺道中は『西海道談綺』で、参勤交代は『一路』に描かれていたが、本書の話を知っていれば一層面白味が増す。学術性は薄いが歴史・時代小説の副読本としては役立つ。2021/12/18
きみたけ
73
著者は主に江戸をテーマに執筆・講演活動を展開、歴史家の安藤優一郎氏。江戸時代は農民も町人も男も女も物見遊山を楽しめた時代であった。太平の世を背景に庶民が牽引する形で国内旅行の市場は拡大し、全国各地に多くの観光地を産み出し旅行産業を活性化させる要因となった。各旅行先で見られた泣き笑いに焦点を当て江戸の旅行ブームの実像に迫った一冊。伊勢神宮へのおかげ参りの裏方として「御師」という旅行代理店の存在があったこと。参勤交代に海路もあったこと。金銭トラブルが頻発し本陣経営は採算に合わないビジネスだったことなど。2023/02/16
molysk
71
江戸中期、日本は空前の旅行ブームを迎えた。ある年には、二カ月の間に三百六十万人近くが伊勢神宮に参拝したという。当時の日本の人口が三千万人台だったので、およそ十人に一人という割合だ。旅行に出たのは庶民だけでなく、大名や武士、公家や外交使節もいた。それぞれの苦労があったが、将軍の威を借る旗本が大名を宿から追い出すなど、穏やかではない。さらには将軍への献上物は、将軍と同じ対応が求められる。将軍に献上する茶を入れた壺が来れば、庶民は後難を恐れて、戸を閉めて引き籠る。「茶壷に追われてトッピンシャン」というわけだ。2022/01/06
樋口佳之
60
庶民の旅行の部分が面白く読めました。講に似た参加者各人が積み立てて年に一度の観光旅行とかあったなあ。この娯楽に富んだ描写を、それぞれの庶民は生涯に何度ほど体験していたのかを知りたい。2021/12/08
-
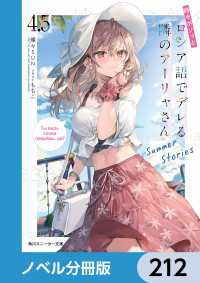
- 電子書籍
- 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリ…
-

- 電子書籍
- イタリア人の女の子が居候することになっ…



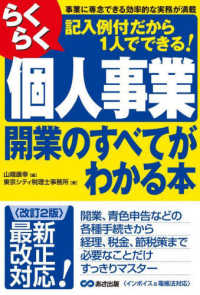
![Studio [21] - Grundstufe - A1: Teilband 1.Tl.1 : Kurs- und Übungsbuch - Inkl. E-Book. Niveau A1 (Studio [21])](../images/goods/ar/work/imgdatak/30652/3065205300.jpg)


