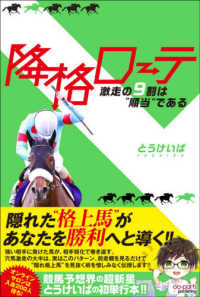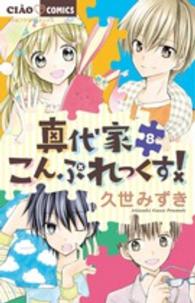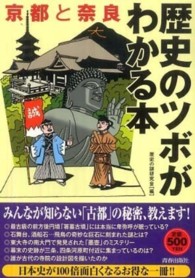出版社内容情報
南北朝の内乱は、古代社会を崩壊させ、封建の新時代を築き上げた。この内乱の推移を、南朝方の結城宗弘、楠木正成、後村上天皇、北朝方の足利尊氏、佐々木道誉、足利義満に焦点をあてて平易な文章で綴った「南北朝」入門書。
内容説明
後醍醐天皇―古代律令国家再現を夢見た異形の帝。楠木正成―南北朝随一の軍略家の栄光と悲劇。足利尊氏―“逆臣”と呼ばれた室町幕府創設者の真実。佐々木道誉―傲岸不敵な婆娑羅大名の典型。足利義満―国内統一を成し遂げ、「日本国王」を称する。かつてない大乱の全体像と当時を生きた人物の息づかいまでもが手に取るようにわかる一冊!
目次
序章 内乱の前夜
第1章 結城宗広―東国武士の挙兵
第2章 楠木正成―公家勢力の基盤
第3章 足利尊氏―室町幕府の創設
第4章 後村上天皇―吉野朝廷の生活
第5章 佐々木道誉―守護大名の典型
第6章 足利義満―国内統一の完成
付章 内乱の余波
著者等紹介
林屋辰三郎[ハヤシヤタツサブロウ]
1914年石川県生まれ。京都大学文学部国史専攻卒業。立命館大学教授、京大人文科学研究所教授・所長、京都国立博物館長等を歴任、京都市史編纂に従事。98年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
47
6人の人物を通して南北朝時代を解き明かします。ある程度戦国時代の知識がないと難解に感じるかもしれません。豊富な資料を多角的に見つつ、客観的に淡々と述べている印象を受けました。これを踏まえて太平記が読みたくなります。2025/05/05
to boy
28
中世日本史にまったくの初心者なので楠木正成や足利尊氏などの人物についてどんな人物なのか少しだけ分かった(ような気がした)。南北朝時代ってほんとに政治的にも経済的にも混乱していたんですね。古代でも中世でも天皇と貴族、武士たちの勢力争いはあったけれど天皇制を廃止しようとする考えが無かったという事が今の日本の礎にもなっているのかなって思いました。2021/04/13
Tomoichi
26
帯に「名著復刊!」になっているだけあって、重要人物にフォーカスして語られるので、南北朝時代を理解するのは良い本ですが、初版が1957年昭和32年なので、引用される資料に対して読み下しがないので、学の無い私には厳しい。漢文で書かれたものなんて、レ点とかちゃんと高校の漢文の授業を聞いていればと。(ひたすら漢文暗記させられた記憶しかない)引き続きこの時代の本で室町時代復習進めます。2025/08/02
ロビン
19
初版が1957年という歴史ある本の復刻新書版。東国武士の結城宗広、著者が「日本史で人気者を3人あげよといわれたならば、・・まず義経と秀吉をあげ、それから正成をあげる」と書く楠木正成、室町幕府創設者の足利尊氏、戦乱に翻弄された後村上天皇、茶道、華道、狂言に通じた<バサラ大名>佐々木道誉、史上初めて征夷大将軍と太政大臣を兼ねた足利義満と、6人の人物を通して南北朝時代を通覧する内容となっている。観応の擾乱時に尊氏による直義毒殺説をとるなど、既読の歴史本と見解が異なる箇所もあった。全体に難しかったがためになった。2022/05/30
moonanddai
9
南北朝期の登場する人々、つまり宮方、武士方双方とも全く一枚岩でないところから事が動いているのが面白かったし、経済的社会的な背景も参考になった。恥ずかしながら初めて知った言葉が「散所」。散所とは「年貢を予定しない土地」を言うようで、そこは荘園(正確にはそこの年貢)を武士に奪われた天皇や貴族(寺社も?)につながる場所で、運送業務、漁労、狩猟、特産物の生産といった雑役に従事する人々が住み、天皇らとの経済的関係ができる。つまり(筆者はそこまで言っていませんが)そこが「アジール」となると私なりに理解したのですが…。2023/11/30