出版社内容情報
認知症の症状と向き合って40年。医療・福祉関係者に広く使われている「長谷川式認知症スケール」の開発者として世界的な名医が、認知症の基礎知識と最新情報をわかりやすく解説する。診断、治療、介護、予防など、家族の悩みや疑問に答える。
内容説明
アルツハイマー型、血管性、レビー小体型―認知症の正体は?治療薬の開発は?ストレスがたまらないケアの方法は?家族も認知症の人も、安心して暮らせる「町づくり」とは?基礎知識から最新情報、将来への提言まで、丁寧に説明。医療・福祉、行政関係者にもお奨め。
目次
序章 「認知症でつながる絆」をつくろう
第1章 認知症とは何か
第2章 診断のプロセス
第3章 治療の方法
第4章 認知症を予防する
第5章 新しいケアの方法
第6章 若年性認知症とは
第7章 看取り
第8章 ポピュレーションアプローチ
終章 見守りの町づくりが社会を明るくする
著者等紹介
長谷川和夫[ハセガワカズオ]
1929年生まれ。認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長。東京慈恵会医科大学卒業。同大学助教授、聖マリアンナ医科大学教授、学長を経て、同大学名誉教授。医療・福祉の現場で使われている「長谷川式認知症スケール」を40年前に開発し、「痴呆」から「認知症」への名称変更を推進するなど、この分野の第一人者。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
-

- 電子書籍
- クズな夫を処分します ~私にはもう不要…
-
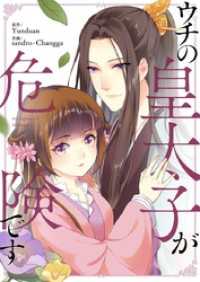
- 電子書籍
- ウチの皇太子が危険です【タテヨミ】第6…





