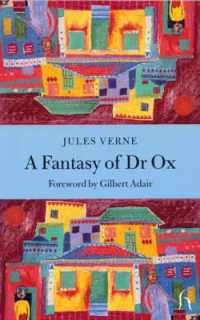出版社内容情報
邪馬台国九州説を追跡し、古代史の大いなる謎を解く。魏によって死を迫られた卑弥呼、その墓は? 神武天皇東征は何を物語るのか? 日本のルーツの現場を探訪する。大御所・森浩一ロングインタビューも収録。大好評『激変!日本古代史』第2弾。
内容説明
邪馬台国、出雲、ヤマト王権―最も新しい仮説を追って日本の原点を見た!対馬・壱岐で、大海を自在に渡った島びとの繁栄を確かめ、玄界灘沿岸では、女王国の中核の国ぐにの生活をしのぶ。火の国九州を、謎を解き明かすべく南へ北へ。さらには神話の舞台出雲から、「まほろば」ヤマトへ。ノンフィクション作家が、日本のルーツに肉薄する。
目次
1 倭人伝を歩く(森浩一氏・特別インタビュー「卑弥呼は死を迫られた」;中継貿易で栄えた島、対馬・壱岐;玄界灘沿岸、女王国の中核・伊都国と奴国;南九州で独自文化を育てた投馬国と狗奴国;卑弥呼はどこに眠るのか?)
2 古事記を歩く(ヤマトタケル物語は『日本書紀』となぜ違う;ヤマト王権と対立した古代出雲の盛衰;日本海交易圏と出雲の「人気製品」;天孫降臨の古代日向「もう一つの顔」;神武天皇はなぜ、畿内まで東征したのか?)
著者等紹介
足立倫行[アダチノリユキ]
1948年、鳥取県境港市生まれ。早稲田大学政治経済学部を中退して世界を歩き、週刊誌記者を経てノンフィクション作家に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
29
図書館本。日本書紀は朝廷を牛耳った藤原不比等が編纂させたので勝者の記録である。古事記はそれ以前に作られたもので、日本書紀とは微妙に違う内容を持つ。ただ、ヤマト政権が九州から畿内に東遷したものだとする点はほぼ同じである。倭人伝に出てくる邪馬台国はどう読んでも北九州にあったとしか私には思えないが(著者の意見も同じ)、その邪馬台国が東遷してヤマト政権になった歴史的事実を日本書紀も古事記も取り上げているのだと思う。しかし、この説は今では少数派だそうだ。弥生時代後期の大型遺跡が畿内で発掘されているからのようだ。2016/06/18
kokada_jnet
2
古代史ルポ第二作。前作同様に、各発掘地の地元の考古学者に話を聞いているのだが、「通説と違って○○だと思います」と、地元ならでなのオルタナな意見が出てくるのが面白い。2014/04/23
Machina Sapiens @人工無能
1
「日本書記」の背景を伺うため、中国の魏氏倭人伝と古事記を読み解く。って言うことで、所縁(と思われる)の地を訪ね歩く、ルポライト。邪馬台国畿内説、九州説双方平等に扱っている。なかなか興味深い。2012/12/23
Seizou Ikeda
0
倭人の文献史学的解明はもはや行き詰っているように見える。中国の漢、魏、東晋、宋、隋などの歴代王朝の史書に「倭」、「倭人」「倭国」と記された倭人は、自前の文字を持っていなかったがゆえに、どのような文化、社会を持っていたのかを知る手がかりは、それらの文献の中でしか推測できないからである。8世紀以降に作られた『日本書紀』、『古事記』以下の日本の史書は、倭人について、すでにこれら中国の文献や朝鮮の漢字による文献を参考にするほかなかったようである。 倭国、倭人に関する文献学的探究は江戸時代以来、ほとんど余すところな2013/06/19
Jimmy
0
なかなか素人に読ませる古代本としては良いツボを押さえていると思いました。著者自身が素人と自覚し、専門家の仮説に寄りながら現地探査を試みる、これこそ私の余生の楽しみ、って感じで上手いアプローチです。2013/06/16