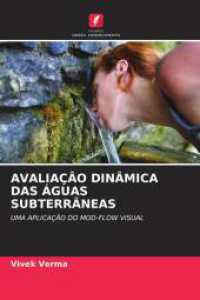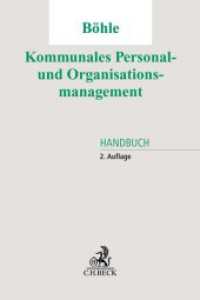内容説明
コシヒカリ誕生から半世紀。全国の作付面積は40%近くにも及ぶ。だからこそ、このブランド米には数々の弊害がある!次世代の米を探求する植物遺伝学の第一人者が、最新の研究成果を解説し、生物多様性と米作りの未来を考察する。
目次
序章 スーパースターの素顔
第1章 コメの「うまさ」とは何か
第2章 コメの品種はどのように作られてきたか
第3章 コシヒカリの寿命
第4章 生物多様性と多彩なコメ文化
第5章 偽コシヒカリ問題
第6章 地球温暖化とイネの将来
第7章 ポストコシヒカリ時代がやってきた
著者等紹介
佐藤洋一郎[サトウヨウイチロウ]
1952年和歌山県生まれ。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。農学博士。専攻は植物遺伝学。国立遺伝学研究所助手、静岡大学農学部助教授などを経て、総合地球環境学研究所副所長・教授。稲の起源、伝播の研究に長年携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
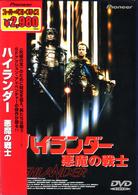
- DVD
- ハイランダー 悪魔の戦士