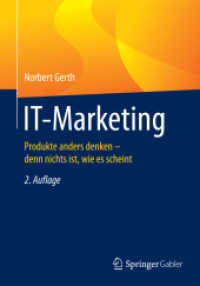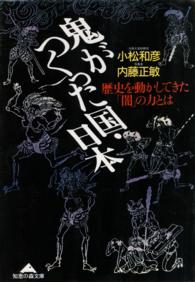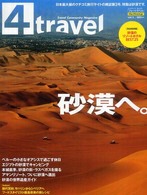出版社内容情報
『漢方小説』から14年。「院内カフェ」は病院にありながら、治療の場ではなく、出入りする人びとがさまざまな思いをかかえて一息つける大事な場所だ。人生の困難がいや応なくおしよせる、ふた組の中年夫婦のこころと身体と病をえがく長編小説。
内容説明
「ここのコーヒーはカラダにいい」と繰り返す男や、態度の大きい白衣の男が常連客。その店で働く亮子は売れない作家でもある。夫との子どもは望むけれど、治療する気にはなれない。病院内カフェを舞台にふた組の中年夫婦のこころと身体と病を描く長編小説。
著者等紹介
中島たい子[ナカジマタイコ]
1969年東京都生まれ。多摩美術大学卒業。放送作家、脚本家を経て、2004年『漢方小説』で第28回すばる文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件