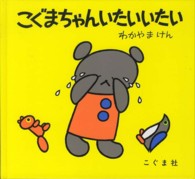内容説明
日本人の先祖の一派で、5~10世紀に北海道を拠点に活躍したオホーツク人。幻の海洋民族の痕跡をたずね、著者は稚内、枝幸、常呂、網走などを歩いた。少年時代からの考古学ファンで、さらに雄大な北海道考古学の世界に魅せらせる。「雪の季節に北海道に行ってみたかった」という一行そのままに、ゴム長姿で雪を蹴散らし、地元に溶け込んでいく。
目次
縄文の世
モヨロの浦
札幌の三日
北天の古民族
韃靼の宴
遙かなる人々
アイヌ語学の先人たち
マンモスハンター
研究者たち
木霊のなかで:樺太からきた人々
宝としての辺境
花発けば
ウィルタの思想
コマイ
アイヌ語という川
遠い先祖たち
チャシ
貝同士の会話
雪のなかで
声問橋
宗谷
泉靖一
林蔵と伝十郎
大岬
大海難
黄金の川
佐藤隆広係長
紋別まで
森の中の村
小清水で
町中のアザラシ
斜里町
斜里の丘
流氷
旅の終わり
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
28
○訪れたことはありますが、歴史的な部分は何も知らなかったので楽しみながら読めました。マンモスハンター、研究者たち、林蔵と伝十郎、大海難、黄金の川、小清水でが良かったです。2022/03/28
さつき
17
ムック本『司馬遼太郎の街道をゆく2』を見てオホーツク人の存在を知り、本編も読んでみたくなり手に取りました。北海道オホーツク海沿いに住み海の恵みに寄って生きた狩猟採集民で、アイヌ文化に先行し影響を与えただろうとのこと。極寒の地で竪穴式住居で暮らしていたのかとまずはそこで驚いでしまいました。が、様々な食料をもたらしてくれるオホーツク海があり、狩猟採集をする人にとっては生きやすい場所だったとのこと。他にも山靼貿易の話し、江戸時代の樺太探検の話し、昭和14年のソ連船遭難事件など興味深いエピソードが多かったです。2015/12/05
はちこう
16
日本人のルーツについて考えさせられた。縄文人の末裔がアイヌとのこと。アイヌこそが日本列島の先住民の末裔ということになる。そのアイヌに対し差別があったことや、文化的にも人口的にも消滅に向かいつつあることは残念でならない。どうか、消滅することなく永く存続しつづけて欲しいと思う。本巻では歴史的に有名な人物としては、間宮林蔵くらいしか登場しない。その代わりといっては何だが、モヨロ貝塚の発掘に貢献した米村喜男衛の名が何度も登場する。献身的な奥様とのエピソードが微笑ましかった。2024/12/21
mam’selle
16
数ある街道をゆくの中でもアカデミックな深掘りが顕著な作品だと思った。先月末に道東旅行帰ってきてから本作を読んだが、先に読むべきだった。旅行では網走市の道立北方民族博物館のオホーツク人など狩猟民の展示が圧巻だったが、司馬さんの解説を読んでから行けば、100倍面白かったはず。 司馬さんの歴史小説は中世から近代が多いけどれど、本州の縄文から弥生時代、北海道でのオホーツクから擦文文化、アイヌと、全く異なる時代変遷を初めて知る事が出来た。 またまた北海道旅行に行きたくなる一冊です。2022/09/30
時代
16
オホーツクをゆく。歴史というよりは、考古学的な観点からアイヌ、オホーツク人はどこから来たのかを考える。正直興味が湧かずで手強かった△2019/03/15