内容説明
「文七元結」「大山詣り」「富久」といった落語を思い出しつつ、本所・深川を歩く。三遊亭円朝、三代目柳家小さんのあとは、夏目漱石、芥川龍之介が登場する。落語から明治の近代文章語の成立に話は移っていく。深川っ子の次は神田っ子。本の町神田は著者のなじみでもある。古書街の英雄たち、この町で勃興していく学問の担い手たちが描かれる。近代日本を知的に支えた町でもあった。
目次
本所深川散歩(深川木場;江戸っ子;百万遍;鳶の頭 ほか)
神田界隈(護持院ケ原;鴎外の護持院ケ原;茗渓;於玉ケ池 ほか)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『竜馬がゆく』、『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
k5
67
江戸力強化月間⑤。東京を描くとあまり高揚感がないのは、つくづく関西の人だなあと思う。それでも落語を中心に語られた本所深川と、学問出版のメッカとしての神田界隈では景色がまったく違ってくるのはさすがというところです。ご本人が文中で「落語好き」とおっしゃってますが、一読すると神田の方に親和性が高い気がします。2022/05/11
Book & Travel
47
【司馬遼太郎の二月@菜の花街道まつり】司馬さんの東京紀行は、本所深川と神田界隈。どちらも自分の通勤経路から遠くないのだが、古書街に数度行ったぐらいだ。落語と橋で巡る本所深川と、学びの町・神田の歴史。膨大な情報量に圧倒されつつ、様々な人と時代が織り成す歴史話を楽しんだ。特に司馬さん自身もよく利用した古書街の歴史は力が入っているようで、出版と本に力を尽くした人々の話はとても興味深かった。多くの学校ができた神田ならではの医学や法学の歴史も面白い。一度ゆっくりこの界隈を歩き、学びのまちの空気を味わってみよう。2018/02/12
kawa
35
神田界隈は若い頃の生息地域、本所深川は上京のおりの下町散歩で馴染みの地でどちらも楽しく読了。隅田川六大橋(相生、永代、清州、蔵前、駒形、言問)に改めて注目。神保町古書店を巡る驚愕の名人「三人の茂雄」も面白い。岡茂雄は我が郷土出身、「本屋風情」を手配。明治の世での落語の書き下しが、現在使われている文章語の始まりというのも初知り。円朝の「文七元結」をユーチュ-ブで早速のお楽しみ。2021/09/03
rena
32
深川の木場の辰巳芸者がキップが良くて羽織を着た男装していた。おキャンななどという言葉は、侠のこと。 富岡八幡宮は、社領が与えて上げられないので富くじや勧進相撲などでお金が入るよう徳川幕府(綱吉の時代)から優遇されたとか、隅田川にかかる橋も橋の形がみな違う話など興味が尽きない。街道をゆくシリーズも身近なところから読んでいくと 馴染みやすいのではないかと思ったり、博学になったような心地がして散策にこの本もお勧め。2017/03/30
金吾
26
司馬遼太郎さんの博識ぶりと筆力に圧倒されます。神田は中学・高校の時に古本屋を覗きによく行きましたが、本屋の話も結構あり楽しかったです。明治期の神田界隈の学校の話も面白かったです。2021/11/05
-
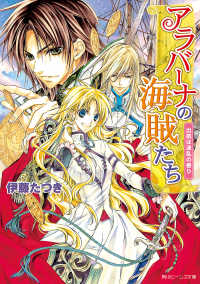
- 電子書籍
- アラバーナの海賊たち 〈出航は波乱の香…




