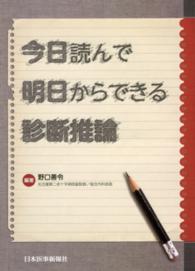内容説明
いまなお妖精の棲む「アイルランドの中のアイルランド」に、いよいよ足を踏み入れる。アラン島に象徴される荒れ地と英国支配のくびきが育んだ信仰、孤独、幻想…。そして、それらアイルランド的な性格なしには生まれ得なかった文学。「山河も民族も国も、ひとりの“アイルランド”という名の作家が古代から書きつづけてきた長大な作品のようでもある」という感慨とともに旅は終点へ。
目次
ジャガイモと大統領
ケルト的神秘
百敗と不滅
ゲーム語
『静かなる男』
須田画伯と“アラン島”
ゴールウェイの雨
イルカのお供
カラハと葬送曲
岩盤の原
妖精たちの中へ
妖精ばなし
蔦がからむ古塔
城が島
峠の妖精
甘い憂鬱
森の聖地
日本びいき
大戦下の篭城者
フォーク・グループの演奏会
神と女王陛下
ジョセフ・P・ケネディ
表現の国
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
燃えつきた棒
35
十九世紀半ばにおこった「大飢饉」(ジャガイモ飢饉)について 【当時、アイルランドはまだ“英国”だった。 その大飢饉は一八四五年におこり、四九年までつづいた。そのあいだも、入札小作人たちは、借用耕地の三分の二で収穫される小麦を英国系の地主に納めつづけたというから、そらおそろしい気がする。 ー中略ー 大飢饉は、九百万人の時代におこった。百万人が餓死し、百五十万人が、(略)アメリカ(一部はイギリス)に移民したのである。】/2022/07/08
はやしま
33
【司馬遼太郎の二月】Iに続きプロテスタントとカトリックの関係、ジョイスやイェイツ他の文学作品を通して愛蘭を見る。ややそこに視点が固定されている感も。連載途中で文学に依り過ぎていると指摘を受けていた由。岩だらけの土地に住む人々。「人間もタンポポとおなじなんですね。種子が落ちたところが極楽だと思って住んでるんですね。たとえ極楽だとおもわなくても、勇敢に住みつづけるんですね。そこが人間の偉大なところですね」(p.67,l7-9)。須田氏の言葉が慧眼。WWII中ダブリンに日本の領事館が置かれた話が興味深かった。2018/02/10
かず
27
一行は、リヴァプールから首都ダブリンに渡り、一路大西洋を目指す。そして、洋上のアラン島に渡り、帰島、南部を周遊し、ダブリンに戻る行程を辿る。感想。私は文学に疎いので、アイルランド文学の巨匠であるジョイスやベケットについての記述には特段の感想は持たなかった。よって、文末の「訪れなくとも、これらを読めば理解に足る」という点について、なんらの共感もない。しかし、「100敗しても無敗」と信ずる不屈の闘志は気に入った。差別の中からケネディやレーガンは産まれた。それだけで、私は彼の国に愛着を感ずるのである。2019/08/11
金吾
23
著書とともにアイルランドに行ったような気になる作品です。怠惰と無気力、百敗と不滅、独り仕事に向いている、イギリスに対する反発等被抑圧民族としてのアイデンティティに溢れているように感じました。妖精の話も良かったです。2021/02/08
yokmin
19
司馬遼太郎のおかげで、アイルランドに関しては随分と物知りになった。めまいがするほどだ。司馬氏が訪れた1987年ごろは貧しい国であったようだ。その後、外資導入、外国企業誘致を熱心に行い、今や一人当たりGDP では世界トップクラスになった。ただし、GDPと所得の乖離問題は存在する。⇨ GDP と所得の乖離が続くアイルランド経済 ~外資による輸出で GDP は高成長も、所得の増加につながらない状況が続く~(三菱UFJリサーチ&コンサルティング・レポート 4/22/24)2024/12/08
-
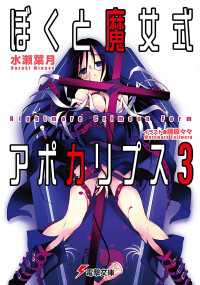
- 電子書籍
- ぼくと魔女式アポカリプス3 Night…


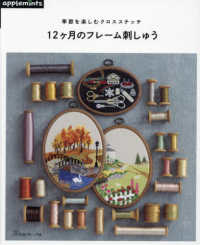
![ライトノベルの新潮流 - その進化と変容の道筋を読み解く! [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866365366.jpg)