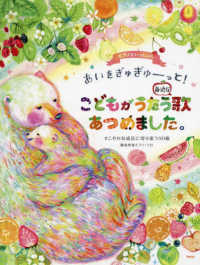内容説明
「私が韓国にゆきたいと思ったのは、十代のおわりごろからである」―宿願をはたすため、いまだ“日帝支配三十六年”の傷口の乾かぬなかをゆく。素朴な農村をたどって加羅・新羅・百済の故地を訪ね、「韓」と「倭」の原型に触れようとする旅は、海峡をはさんだ両国の民が、はるかいにしえから分かちがたく交わってきたことを確認する旅でもあった。
目次
加羅の旅(韓国へ;釜山の倭館;倭城と倭館 ほか)
新羅の旅(首露王陵;新羅国;慶州仏国寺 ほか)
百済の旅(大邱のマッサージ師;賄賂について;洛東江のほとり ほか)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪外国語大学)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





チョンジョの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
molysk
63
1971年に韓国へ渡り、加羅・新羅・百済の足跡を中心に朝鮮史をたどる。朝鮮と日本の歴史が対比される。共に中国から律令国家の仕組みを取り入れたが、日本では武士の勃興で朝廷が実権を失ったのに対して、朝鮮は近代にいたるまで王朝による中央集権型の官僚制を保った。武装農民である武士は地に足のついた文化をはぐくみ、儒教による倫理が支配する文化とは大いに異なる発展を遂げたとする。朴正煕政権下の韓国はいまだ貧しく、農村部では韓のくにの原型をとどめていたようだ。現地の人との会話に、日本支配の生々しい傷跡が垣間見える。2023/07/26
さつき
63
先に『砂鉄のみち』を読み、司馬さんの朝鮮半島への熱い思い入れを知り興味を持ちました。今まで何となく避けていた巻でしたが、色々驚きの連続で面白かったです。旅の途中で出会う強烈な人物や出来事に、不愉快を感じるどころか、どうしてそうなってしまうのかあくまで理解しようとする司馬さんの意志に感服します。秀吉の朝鮮出兵で降伏し、以後朝鮮側に付き戦った沙也可という武将の物語は特に印象的でした。2018/07/29
kawa
49
日韓大騒ぎの時期に読了。長い歴史から見ると中国が親、朝鮮が兄、日本は弟ということか。そういう意味で言うと、明治の時代の日本の朝鮮に対する様々なおせっかいは、お品の悪い行動と兄は見ていたのだろう。兄のげんこつに、弟が飛び蹴りで返した今の図。親もあてにできないのだから、ほとぼりを覚ますしかない。売らんかなマスコミが騒ぎすぎ、それが不幸だ。2019/08/04
Die-Go
33
図書館本。韓半島の旅。百済と新羅の戦いから思いを馳せ自由奔放に考察をする。いいねぇ。 唐や高句麗との四つ巴の(日本はほぼ部外者)半島の歴史を振り返る。人によって今だに国々の好みはあるのね。 面白かった★★★★✩2025/04/28
藤瀬こうたろー
32
レーダー照射で彼の国とゴタゴタしている昨今、タイムリー と言えばタイムリーかもしれません。しかし、司馬先生、要所要所で横道に逸れた話をされますが、これがまた面白い。日本とアメリカにおける個々の兵士観の違いとか、金や李などの姓名に出自があるという話とか、もう珠玉としか言いようがないです。ガイドさんまでうまく話にからめたり、と最早名人芸の域に達してます。取材はおそらく昭和40年~45年位の頃?まだ、「戦後の記憶」は生々しい時分です。もし、今司馬先生が生きてたらお隣の国との関係、どう評してたでしょうね。2019/01/06
-

- 電子書籍
- ゼニ番付 分冊版 2 アクションコミ…