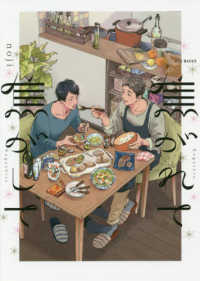内容説明
不世出の人・高田屋嘉兵衛への思いを語った「『菜の花の沖』について」や、魅力的で美しい日本語のあり方を真摯に説いた「言語の文明」など、円熟味を増した闊達な語りが冴え渡る、著者62歳から65歳までの講演19本に、未発表講演(1988年)を追加収録したシリーズ第3巻。
目次
一九八五年(松陰の松下村塾に見る「教育とは何か」;『菜の花の沖』について ほか)
一九八六年(義経と静御前;奄美大島と日本の文化 ほか)
一九八七年(文学から見た日本歴史;三河と宗教 ほか)
一九八八年(1)(横浜のダンディズム;人間という「商売」の話 ほか)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年大阪府生まれ。大阪外国語学校蒙古語部卒業。60年「梟の城」で第42回直木賞を受賞。75年芸術恩賜賞受賞。93年文化勲章受章。96年死去。主な作品に、『国盗り物語』(菊池寛賞)『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)『ひとびとの跫音』(読売文学賞)『韃靼疾風録』(大仏次郎賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
57
2014.01.18(01/12)(つづき)司馬遼太郎著。 01/16 (p186) バルザックの時代、どんどん地下道を掘る。 下水です。 世界一の下水完備の街になりつつあった。 バルザックのある小説が進行すると、地下道の場面が続く。 何ページも。 これも家具と同じ。 家具も、地下道も、小説という船の、浮力をつけるためのもので、ブイのようなもの。 浮力をほかのものに求める。 小説では、このように夾雑物で出来上がっております。 小説とは何でしょう。 2014/01/18
i-miya
48
2013.12.12(12/12)(つづき)司馬遼太郎著。 12/05 (p164) 縄文人、8000年の歴史、何語?おそらく南方語。 台湾の山地人、ミクロネシア人、ハワイのポリネシア人言語、日本人に分かりやすい。 母音が主体の言語、英語の速記者、子音だけを速記すればいい。 アラビア語の蝶が飛ぶような文字、ほとんどが子音。 世界中のほとんどの言語、子音。 朝鮮の人もそう。 綺麗に子音を発音する。 日本人、ドッグ、というときに、ドッグウとなる。 2013/12/12
香取奈保佐
45
司馬遼太郎さんの講演集、3冊目■人々が簡単に参加できる普遍的なものが「文明」、非合理で込み入ったものが「文化」……。たびたび出てきた話だが、司馬さんがそこにこだわった理由が分かった■コラムにある。何かに寄りかかれず、裸眼でものを見なければいけない時代が到来した。だから、人の根底を造りあげる文明・文化について考えないといけない――■そう考えると、大陸や日本の諸藩を比較しながら進む講演の、なんと実り多いことか■後世を思う。日本語は未成熟な言語なのだと知り、美しくしようという意識が芽生える。これも歴史の効能か。2021/10/03
i-miya
45
2013.11.10(2013.11.10)(つづき)司馬遼太郎著。 2013.11.10 (p162) (清朝の愛染覚羅氏もツングースです、つづき) ウラル・アルタイ語族。 ウラル山脈近くの遊牧民族。 しまいにはフィンランド、ハンガリーまでいってしまいました。 西-ウラル語族。 東に留まる-アルタイ語族。 18.19Cはシベリア探検ブーム。 満州、沿海州あたりのツングース、アルタイ語族ですが、ロシア人からみるとよくわからない。 お前たち、何者?あーじゃ、こーじゃ、というが、よくわからない。 2013/11/10
油すまし
41
竹山洋さん脚本のNHKのドラマ『菜の花の沖』を数ヶ月前にテレビで見て、高田屋嘉兵衛についての司馬さんの講演の記録を読みたくなりました。「『菜の花の沖』について」が収録されていたので、図書館で借りました。江戸時代を通じて一番偉かったのは高田屋嘉兵衛だと。それも二番目が思いつかないくらいに偉い人だと。いま生きていても、世界のどんな舞台でも通用できる人、世界史的に見ても偉い人と話されている。『菜の花の沖』も読んでみたい。2023/11/15
-
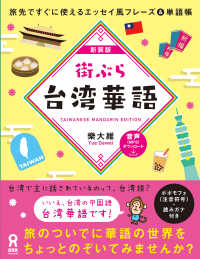
- 電子書籍
- 新装版 街ぶら台湾華語