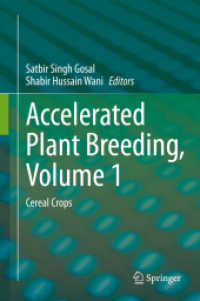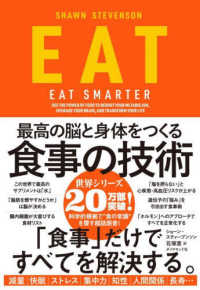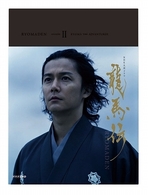感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
63
2014.01.22(01/22)(つづき)司馬遼太郎著。 01/22 (p050) 他力といっても他人の力という意味ではない。 自らの力によらず、仏の力によって救われることをいう。 南無阿弥陀仏を称えればお浄土に参ることができるのです。 自分たちは、お浄土、弥陀の本願に生かされている。 たとえ、弥陀の本願から逃れようとしても、やっぱり生かされている。 南無阿弥陀仏を称えなくても生かされている。 どういう悪人でも救われる。 2014/01/22
i-miya
55
2013.12.17(12/17)(つづき)司馬遼太郎著。 (p048) 野狐禅とはよくいったものですね。 禅とは、危険な思想であります。 昔、マルクス主義が危険だといわれたが、もっと根源的な意味で人間として最も危険な劇薬の部分を持つ。 文藝春秋の講演会で但馬へいったとき、水上勉さんといっしょだった。 友人の水上さんに聞きました。 禅宗に詳しい人。 禅宗のお寺に行きました。 禅宗と言うものは、むつかしい。 禅は、やったほうが悪くなる気がする。 2013/12/17
i-miya
52
2013.11.14(2013.11.14)(つづき)司馬遼太郎著。 2013.11.14 (法然さん) 法然は、「絶対他力」ということを考えた。 偉大なる自然。 偉大なる宇宙というもの。 そういう力に生かされている。 という思想がある。 釈迦の悟りの境地は、絶対他力の境地である。 その境地に信仰によって一気に入れる道がある、浄土門である。 浄土門の得心者は、悟りの境地に入ることができる。 その道筋を開いたのが法然である。 その偉大さは禅宗を考えればわかる。 2013/11/14
香取奈保佐
51
ほとんどの小説を読んだ司馬遼太郎さん。講演は講演で、味がある■歴史観、創作論、人物評が小気味よく織り交ぜられ、生で聞けたらさぞ面白かっただったろう。よく、こんなに喋れるなと。もとより、読者に話しかけるような筆致が司馬作品の魅力であった■史実は「一片の履歴書」。そこに奥行きのある人の像を浮かび上がらせるため、史実を触媒にして想像を膨らませる。こうして数々の名作は生まれたのかと、再読したくなる■「小説というものは、迷っている人間が書いて、迷っている人間に読んでもらうもの」。読み終えて、何箇所も書き写した。2021/09/05
i-miya
41
2013.07.20(再読)司馬遼太郎著 2013.07.17 (解説=関川夏央) 強い違和感、(1)大学構内で感じた「思想」と、(2)大学構外の世相―完全に遊離していること、実感。 (1)戦中、破滅へひた走る一途さも、(2)戦後の不安定さも、いずれも「思想」という酒精分のもたらしたもの。 司馬は、大学よりも、寺を好んだ。 たいていの僧と宗論を戦わせることができる彼の仏教感。 『街道をゆく』は、現実の地図を見て、山川谷風の自然が人事を決定付ける歴史をつくる。 2013/07/20