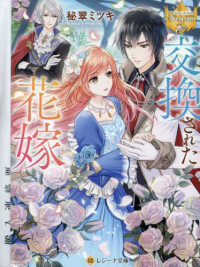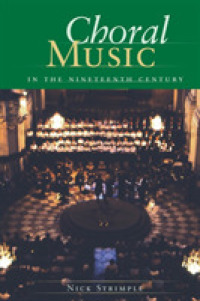出版社内容情報
関ヶ原ののちに豊臣家や豊臣家の西国大名を封じ込めるために、家康が築いた城郭群の数々。その中には、名古屋城や姫路城など、日本を代表する名城も多い。それらを大坂城包囲網として実際に訪ね歩き、関ヶ原から大坂の陣までの時代の移り変わりと、包囲網の実態を探る歴史エッセイ。第一章 伏見城第二章 姫路城第三章 今治城、甘崎城第四章 下津井城第五章 彦根城第六章 丹波篠山城第七章 名古屋城(一)第八章 名古屋城(二)第九章 伊勢亀山城第十章 津城、伊賀上野城(関連年表付き)
内容説明
「大坂城包囲網」とは、関ヶ原合戦以後、豊臣家や豊臣系の西国大名を封じ込めるために徳川家康が築いた城郭群のことである。伏見城、名古屋城から下津井城、今治城まで、なぜ家康はそれらの城を築いたのか。実際に訪ね歩き、15年にわたる持久戦と、家康の「長考」の軌跡を辿る。
目次
第1章 伏見城(京都)―豊臣家・豊臣系大名封じ込めの司令塔
第2章 姫路城(兵庫県)―秀吉に天下を取らせた古今屈指の名城
第3章 今治城、甘崎城(愛媛県)―藤堂高虎が精魂込めた傑作
第4章 下津井城(岡山県)―大坂方の弾薬補給を遮断するための防衛ライン
第5章 彦根城(滋賀県)―東西の境目に位置する包囲網の要
第6章 丹波篠山城(兵庫県)―西国で初めて徳川譜代大名を配する
第7章 名古屋城(一)(愛知県)―城普請は豊臣恩顧の大名をねらい撃ち
第8章 名古屋城(二)(愛知県)―三の丸造営だけを後回しにした本当の理由
第9章 伊勢亀山城(三重県)―関ヶ原合戦でも戦場となる
第10章 津城、伊賀上野城(三重県)―藤堂高虎の手により、ついに包囲網が完成
著者等紹介
安部龍太郎[アベリュウタロウ]
1955年福岡県生まれ。歴史小説家。89年から1年間「週刊新潮」で「日本史 血の年表」(刊行時『血の日本史』に改題)を連載しデビュー。2005年『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞、13年『等伯』で直木賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- やり直し聖女は最愛の人のために死を選ぶ…
-
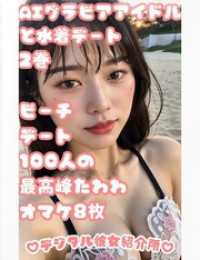
- 電子書籍
- AIグラビアアイドルと水着デート 2巻…