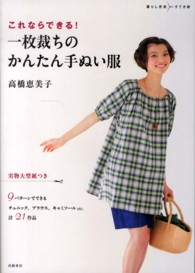出版社内容情報
歌麿が春画で描いた腰巻きや下帯、バリの儀礼用絣グリンシン、日本の着物の生命樹の柄……。江戸から現在へ、布はアジア文化のなかでどのように作られ、流通し、愛されてきたのか。人気江戸学者で法政大学総長の快著。カラー口絵8頁。
内容説明
歌麿が春画で描いた腰巻きや下帯、バリの儀礼用絣グリンシン、日本の着物の生命樹の柄…。布はアジア文化のなかでどのように作られ、流通し、愛されてきたのか?江戸から現在へ―布が結んだ人々の暮らしと心と歴史を、人気江戸学者である法政大学総長が縦横無尽に論じる快著。
目次
1 布をまとう(メディアとしての布;布が意味するもの)
2 織るということ(日本の織物紀行)
著者等紹介
田中優子[タナカユウコ]
1952年神奈川県生まれ。法政大学大学院博士課程(日本文学専攻)修了。法政大学社会学部教授(近世文学)。2014年4月から法政大学総長。2005年紫綬褒章受章。著書に、『近世アジア漂流』『江戸百夢』(芸術選奨文部科学大臣賞、サントリー学芸賞受賞)、『江戸の想像力』(芸術選奨文部大臣新人賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なおこっか
6
布と言っても表層的な話に留まらない。何しろガンジーのチャルカ運動から説き起こされるのだ。歴史の深さ、世界の広がり、人間と社会の本質を、布が明らかにしてゆく。だから人の表面を覆う、着物と表皮を分けて考えるはずもなく、ミイラからオシラサマまで皆登場する。枝葉の豊かな、田中先生らしい講義。『青砥稿花紅彩画』菊之助の啖呵は舞台で生体感したいものだ。堀切辰一氏の著作も、是非読んでみたい。所謂“着物”“和装”ではない、人々の生活着が表すものが知りたい。それから世界樹!ルーツを辿り、各地にどう残されたか見たいモチーフ。2020/05/27
-

- 和書
- スライム桜は異世界に咲く