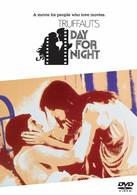出版社内容情報
【文学/日本文学評論随筆その他】正月の門松、雛祭りのモモなど、日本の行事やならわしには、決まった植物が登場する。それはなぜか? 植物の特性と歴史的見地から、行事の原点を解く。すると、自然との結びつきを大事にしてきたかつての日本人の暮らしが見えてくる。
内容説明
四季に恵まれた日本では、古くからある年中行事に必ず特定の植物が登場する。植物の特性と広い歴史的見地を照らし合わせながら、行事の原点を解き明かす。そこにあるのは、縄文や万葉の時代から自然を愛し、時に畏怖し、自然と共存してきたかつての日本人の姿であった。
目次
神と交わる木、マツ
アズキの威力
春の七草の変遷
節分植物を推理する
ウメの香
ツバキ五千年
ひな祭りの背景
花祭りの底流
花見の源流
フジの象徴と実用端午の植物
縁起と忌みに使われるウツギ
ユリの伝統
七夕に神のタケ
アサガオとホオズキの市
多目的作物ヒョウタン
盆の花
秋の七草考
ススキの系譜
サトイモは基層植物
モミジとカエデの国
キクの行事
クリスマス植物の由来
化身の花スイセン
著者等紹介
湯浅浩史[ユアサヒロシ]
1940年兵庫県神戸市生まれ。63年兵庫農科大学(現・神戸大学)卒業。68年東京農業大学大学院農学研究科修了。同育種学研究所所員を経て、東京農業大学バイオセラピー学科元教授。一般財団法人進化生物学研究所理事長兼所長、生き物文化誌学会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てくてく
4
植物の名前の由来、それに関して日本だけではなく台湾などの近隣地域の習俗も紹介されていて楽しかった。但し、やや専門的だったので、読後長い間頭に残っているかどうかは謎。万葉歌人が紅よりも黄色をめでたというくだりや、月見の薄の意味合い(収穫祈願と魔よけの意味を持つ)などが特に興味深かった。2015/10/02
pitch
2
日本人に馴染みのある植物の、暮らしとの関わりについて書いた本。元の本の出版が三十年くらい前なので、もう今となってはちょっとずれてる箇所がなくもないけど、著者の博識にはひたすら感心して読みました。読みやすいし、盛りだくさんで得した気分になれる一冊2024/12/14