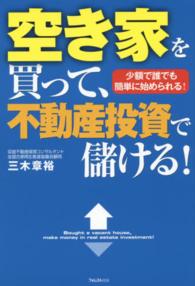内容説明
西南戦争と西郷隆盛を非難する世論の大合唱に抗して、「抵抗の精神」の持続を訴えた「丁丑公論」。勝海舟と榎本武揚の、維新とその後の生き方を批判し、指導者の責任倫理を説いた「瘠我慢の説」。福沢の思想の核心に迫り、真の独立の精神とは何かを問う。原テキストを付録。
目次
1 「丁丑公論」を読む
2 「瘠我慢の説」を読む
解説
関連文献一覧
付録
著者等紹介
萩原延壽[ハギハラノブトシ]
1926年、東京・浅草に生まれる。東京大学法学部政治学科卒業。同大学院修了後、ペンシルヴァニア大学、オックスフォード大学へ留学。帰国後は、研究・著述に専念する。2001年10月没。著書に『馬場辰猪』(吉野作造賞)、『東郷茂得―伝記と解説』(吉田茂賞)など
藤田省三[フジタショウゾウ]
1927年、愛媛県に生まれる。東京大学法学部政治学科卒業。松山高校2年の時、丸山眞男の「軍国支配者の精神形態」に触れて以来、丸山に師事し、戦後を代表する思想家となる。2003年5月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カインズ
1
【政治家の死に方】「権力の偏重」に関して、「専制の精神」と「抵抗の精神」とのバランスを取ったところに活力が生まれるという考え方が印象に残った。講話による一時の利益に勝るものとして、勝ち目が無くても力を尽くして戦う「瘠我慢」という気風からは、合理性を越えたところにある美意識を感じた。今の日本においては、為政者が合理性を言い訳にして「瘠我慢」をしないことが当然になっているように思われる。2012/08/26
1.3manen
0
解説部分で、徳富蘇峰らからの分析が紹介されている。評者は、ラスキンとの関係で蘇峰にも注目しているが、同時代人の時代背景も踏まえてその論を読んでみた。現代日本のように、官尊民卑ではなく、「立国は私なり」(p.212)なのだ。民間活力なのである。現代日本人は、将来の消費増税におびえて、痩せ我慢な経済生活をかろうじて送っている。痩せ我慢は体によくない、と言われるが、当時と現代の痩せ我慢の意味を比較してみるのも乙なものか。2012/05/04
NAGISAN
0
積読本。旅行中に読書。1971年「みすずセミナー」での講演。『瘠我慢の説』で、「立国は私なり、公に非ざるなし」から始まりびっくりさせられた。国家は二義的。衰勢のときには、「瘠我慢」(抵抗の精神)は私情に止まらず「公徳」に転じるという。その点から、勝海舟や榎本武揚の維新後の身の振り方を批判する。福沢の主著からはこのような言説を想像しなかったので新鮮。原著や勝海舟等からの返信、徳富蘇峰の言論等も収録されていてお得感あり。中江兆民や内村鑑三、正宗白鳥、アーネスト・サトウが登場し当時に思いを募らす歴史旅行をした。2023/05/23
ねぎとろ
0
福沢の二篇はさすがに名品とされるだけあって、面白い。これだけ読むと誤解しそうだけども、その辺りは解説でフォローされているので便利な本といえる。福沢の天邪鬼さがよく出ている作品。 それはともかく、批判を送られた勝の返答が見事。やはり大物は違うと感心した。2018/06/04
-
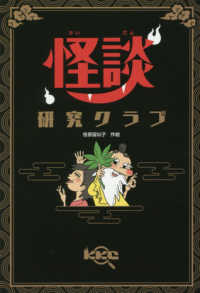
- 和書
- 怪談研究クラブ