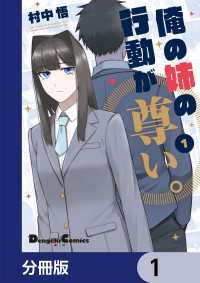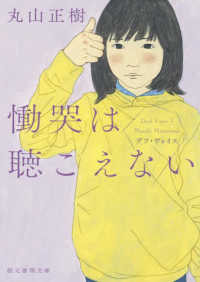内容説明
少女マンガ評論の新境地を拓いた名著、待望の文庫化。1960年代末から90年代末頃までの少女マンガの描写から、女性の恋愛観、セクシュアリティ、家族観、職業観の変化を概観、同時にトランスジェンダーなど性的指向に関する描写の変遷も追う。“居場所”を求めるすべての人必読の書。
目次
恋愛―恋愛という罠
性描写―ことほどかように
成熟―オトナになった少女マンガ
家族―「明るい家庭のつくり方」
居場所―あなたのための場所
時間―“閉じられた季節”の向こう側
トランスジェンダー―女の両性具有、男の半陰陽
レズビアン―女であることを愛せるか
女性愛―時代は明るいレズビアン
社会―お仕事!
組織―女性総合職、逆転ホームラン?
生殖―生殖からの逃走、あるいは世界の再生
生命―緑への意志
進化―存在の変容へ
著者等紹介
藤本由香里[フジモトユカリ]
熊本県生まれ。東京大学教養学科卒。1983年より筑摩書房で編集者として働くかたわら、コミック、女性、セクシュアリティなどを中心に評論活動を行う。手塚治虫文化賞、講談社漫画賞、メディア芸術祭マンガ部門選考委員。マンガ学会理事。2007年末に筑摩書房を退社し、08年4月より明治大学国際日本学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
33
出逢えて良かった本の一つ。題名に惹かれ発売直後に読み、文庫本も買って折に触れ読んできた。中島梓の名著『コミュニケーション不全症候群』編集者のデビュー作。「文庫版まえがき」に<少女マンガを読んで心動かされている時、その裏で働いているのは「あ、わかる」という感覚だ。「私だけじゃないんだ!」という“何かが共有された感覚”だ。その時に感じる安心と喜びと解放感>とある。深く頷く。<私たちは、どういう罠にはまってきたのか。これは、それを探ろうとする試み>だと。私もこの書を読み続けることを通し、試み旅の同行をしたい――2020/01/03
スノーマン
25
ほとんど読んだことのない漫画の紹介が多く出てきたけど、それでも興味深い内容。時代とともに、それまでタブーと言われるような関係性まで描いていった少女漫画の世界。あー、またこのパターンか、みたいな漫画は確かに読みたくないからね。私は普通にりぼんを読んでいたけど、友人からはまた違う世界観の漫画を教えてもらったりしてワクワクしながら貸借りしていたのを思い出す。ざ、ちぇんじ!や、ぼくの地球を守ってとか、りぼんに染まった私を相当驚かせたのを懐かしく思い出した(笑)2018/01/11
きいち
21
60年代~90年代にかけての少女マンガとレディスコミックを通じて、女性たちがいかに自分の「居場所」を獲得してきたか、その闘いぶりを追いかける。性が怖れではなくなったこと、恋愛での自己決定、家族の再定義、仕事での主体性の獲得など、「女たちはここまできたのだ」という何度も叫ばれる肯定の快哉がとても印象的だ。だって本当に、「昔」って暮らしにくそうだもの。◇そして、その先のゼロ年代以降、この闘いは女子だけのものじゃなくなったと思う。男性向け女性向けじゃなく、自分の中の女に響くマンガ、男に響くマンガになったのだと。2014/01/18
さとちゃん
6
1998年に単行本として出版されたものを2008年に文庫として出されたもの。従って、2000年代に入ってからの作品は対象ではない。とはいうものの、本書が取り扱っている作品はいわば少女漫画の黄金期とも言える時代のものではないかと思う。「私の居場所はどこにあるの?」という問いが少女漫画の大きなテーマだ、ということはとても納得のいく話でした。中島梓の論評を読んだときには、そこまで強く感じなかったのだけど、これは私が年を重ねて社会を見る目が深くなったからでしょうか。。。2023/11/23
erie
6
駒場っぽいなと思ったがはたして駒場出身者の論考集。主にクラシックな少女漫画を集め、様々な切り口から考察していて、特にクィア論、仕事について、SFがなかなか面白い。熱情が先行した、ほうっておいても考察し書かずにはいられないタイプの人なのだと思う。ガールズラブの類型とボーイズラブの多様性の対比、組織の中で働く女性の描かれ方、そして性別そのものをSF的にとらえなおそうとする試み。読者が心理的情緒的に何をもとめ、社会の中で少女たちがどうとらえられてきたか。まあ少々古いのは難点だが、読み応えはある。2020/01/13