感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
42
近々北海道を訪ねる予定で3巻から高跳び。北海道の名の由来は、アイヌの人々が自らその地を「加伊(かい)」と呼んでいた音をとり「北海道」とした由。函館ハリストス正教会の老神父「ローマ・カトリックは分派。私たちギリシャ正教・ロシア正教が正統」の弁にも虚を突かれ、なるほど。訪ねたい場所は、その教会、高田屋嘉兵衛の銅像、松前城、江差の開陽丸関係の遺跡、北大ポプラ並木、通行屋、三好好太郎美術館、樺戸集治監、新十津川町、滝川郷土館、旭川郷土博物館(偕行社)、陸別の関寛斎翁の遺跡。旅行予定を根本的に見直さねば?…。2019/08/23
kawa
38
(再読)近々訪問予定の札幌周辺地を再読。旭川市に残る屯田兵家屋の粗末さに「ともかくも、なま身の人間をこういう小屋に入れて寒冷地開拓をやらせた政治家や役人どものおそろしさを記念するという意味でも、この標準兵屋はながく保存されていい。」と憤る司馬先生が印象的。この史跡は今も展示中なのだが、ネット写真をみる限り当時の悲惨さを残しているものか確認できない。2022/03/31
kawa
35
松前行きのために再々読。新幹線木古内駅から路線バスで1時間半の松前町。司馬先生も「ずいぶん遠いですな。」松前城はロシアなどからの進行に備える北辺防備のために日本最後の城として1855年完成。アイヌの反乱をおそれ断崖海岸の矮小な地にあえて建設。軍艦攻撃で木っ端微塵のおそれがあるから城を函館にの意見もあったが、松前藩はこの地に固執。案の定、完成から13年後、旧幕榎本軍の攻撃であっけなく落城。さらに松前から1時間の江差。その地で思わぬ座礁の榎本軍の旗艦・開陽丸。その資料館の見学は時間の都合で残念ながら次回に。2024/06/26
紫羊
35
令和最初の読了本は昭和の大偉業「街道をゆく15/北海道の諸道」でした。どの巻でもそうですが、司馬さんが惚れ込んだ(と思しき)人物が絡むと、それこそ筆が踊っているようで、格段に面白さが増します。あと三分の二、今度こそ挫折しないように最終巻まで積読済みです。2019/05/03
かっぱ
29
シリーズでは「十津川街道」のあとに読んだためか、新十津川村の話は興味を持って読めた。咸臨丸の最後がなんともあっけない。榎本武揚が描いた北の大地での理想郷建設は咸臨丸とともに沈んだように思える。タコと呼ばれる奴隷土工のはなしは何とも残酷。2016/03/27
-

- 電子書籍
- ああ、生きているって素晴らしい【タテヨ…
-
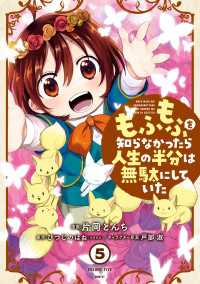
- 電子書籍
- もふもふを知らなかったら人生の半分は無…
-
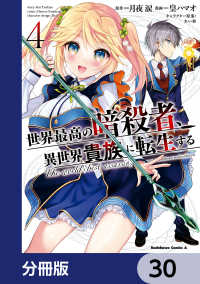
- 電子書籍
- 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する…
-
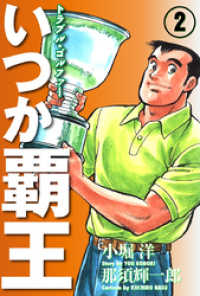
- 電子書籍
- いつか覇王 愛蔵版(2) ゴマブックス…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】柳原くんはセックス依存症…




