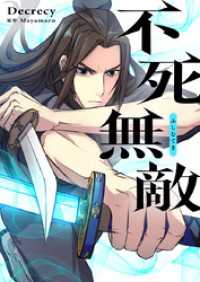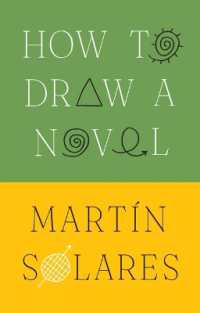内容説明
アウシュヴィッツの灰色の領域で―記憶を風化させる年月の流れ。犠牲者だけが過去に苦しみ、罪ある者は忘却に逃れる。生存者レーヴィの40年後の自死。
目次
1 虐待の記憶
2 灰色の領域
3 恥辱
4 意思の疎通
5 無益な暴力
6 アウシュヴィッツの知識人
7 ステレオタイプ
8 ドイツ人からの手紙
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
56
【新たな道化師だけが待ち望まれている(その候補者には事欠かない)】記憶の風化。犠牲者は過去に苦しみ、罪人は忘却に逃れる。40年の歳月を経て、アウシュヴィッツとは何かを問う書。巻末に、「訳注」と「訳者あとがき」。原書は著者自死の1年前(1986年)刊行。翻訳は2000年。<文化的な国民全体が、今日では笑いを誘うような道化師に盲従したのである。だが、アドルフ・ヒトラーは破局に至るまで、服従と喝采を得ていた。これは一度起きた出来事であるから、また起こる可能性がある。これが私たちが言いたいことの核心である>と。⇒2025/05/13
扉のこちら側
50
初読。著者の死の1年前に刊行された本。著者は作家生命の中で一貫してアウシュヴィッツを論じてきたが、記憶の風化へ、の自省を込めて書いている。善悪の単純な二分では語れない、灰色の領域について。2013/06/30
たまご
17
人間が関わって変化を及ぼす世界の事象は,二項対立ではなくて,グラデーションで推移していき,完全に2つに分けることはできないのでしょう.おそらく,どんな場面でも,相対的に,強者と弱者・もしくは(権力そのほかを)持つものと持たざる者を作り出してしまう.これは社会的生物である人間の,社会性の一つの側面として避けられないことなんでしょうか. あいまいははっきりしなくて嫌ですが,2つに分けるとそこで思考停止してしまうような気がします.嫌だけど考え続けなければいけないのだなあと.2014/09/23
ケニオミ
15
日経の書評を見て手にした一冊です。最近は、余生が限られているせいか、暗い内容のものを受け付けられないようになっているみたいです。本書も半分くらい読んで挫折してしまいました。(結論は読みました。)結論を読んでのまとめですが、一度起こったこと(ホロコースト)は再び起こる。ホロコーストでも加害者は普通の人であった。それを避けるためには、そのような兆候に注意して起こらないようにする努力が必要である。2020/02/24
くれの
14
アウシュビッツを生還した著者の遺作となった一冊です。戦後40年の歳月が過ぎ人々の記憶の風化を危惧する彼の焦りがこの本に凝縮されています。迫害者と犠牲者を単純に二分化する標題の二者の違いは何もないと痛感しました。2021/04/17