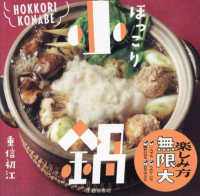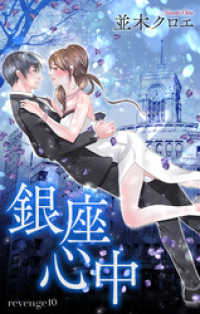内容説明
「読まないと損だよ」―心理療法家が、大人にも子どもにもできるだけ多くの人に読んでもらいたい児童文学の傑作を紹介する。ケストナー、ピアス、ロビンソン、今江祥智、ヘルトリング、リンドグレーン、ゴッデン、長新太、佐野洋子。大人の見落としている「たましい」を子どもの目から捉えた作品が私たちに教えてくれるものとは何か。
目次
なぜ子どもの本か
1 エーリヒ・ケストナー『飛ぶ教室』
2 フィリパ・ピアス『まぼろしの小さい犬』
3 J.ロビンソン『思い出のマーニー』
4 今江祥智『ぼんぼん』『兄貴』『おれたのおふくろ』
5 ペーター・ヘルトリング『ヒルベルという子がいた』
6 A.リンドグレーン『長くつ下のピッピ』『ピッピ船にのる』『ピッピ南の島へ』
7 ルーマー・ゴッデン『ねずみ女房』
8 長新太『つみつみニャー』他
9 佐野洋子『わたしが妹だったとき』
著者等紹介
河合隼雄[カワイハヤオ]
1928年兵庫県生まれ。京都大学理学部卒業。1962年よりユング研究所に留学、ユング派分析家の資格取得。京都大学教授、国際日本文化研究センター所長、文化庁長官を歴任。2007年7月逝去
河合俊雄[カワイトシオ]
1957年奈良県生まれ。京都大学教育学研究科博士課程修了。ユング派分析家資格取得。京都大学こころの未来研究センター教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
47
著者の語る「子どもの本」とは「子どもの目の輝きを失うことのない大人の書いた本」であり、子どもはもちろん、大人も読む価値のある本である。読んだことがあるのは「飛ぶ教室」と「思い出のマーニー」だけだったが、心理療法の専門家である著者の読み方には感心するところが多かった。人間存在を考える上で心と体、それに両者に関わる第三領域の「たましい」が存在すると仮定すると、「子どもの本」の中にこの「たましい」について書かれている本があるという指摘は面白いと思った。シリーズになっているようなので、他の本も読んでみたい。2021/05/19
大先生
13
【人間には、①心と②体、その両者に関わる第3領域としての③たましいがある。大人は常識にとらわれて「たましい」を見なくなるが、子どもは端的に「たましいの現実」を見る。ここに子どもの本の大きい存在意義がある。】とした上で、「飛ぶ教室」「思い出のマーニー」などの名作の中に河合先生が入り込んで、主観的に感じた「たましい」との接触を解説した本です。気軽に読み始めた本でしたが、予想外に深い内容でした。児童文学を舐めてはいけないですね。本書では9冊の本が紹介されていますが、「飛ぶ教室」がイチ押しのようです。2023/02/09
roughfractus02
12
『銀河鉄道の夜』の講演の際、聴衆の1人に体の震えが止まらなかったと言われた著者は、賢治の名作は「どこか体に作用してくる」と述べる。ファンタジー(幻想)に属する児童文学の世界には象徴、魔法、錬金術等ユング心理学の鍵語に満ちているが、著者は心と身体の関係を読者に感覚から触発する点に児童文学の特徴を見る。本書を読むと『飛ぶ教室』の子ども達の喧嘩の場面は、二足歩行に行動を固定し、自我と言葉に世界を制限する教室空間に、子どもの心と身体が作る柔軟な「たましい」(ファンタジー)が反乱するように思える(9作の紹介あり)。2022/12/08
MIHOLO
11
河合隼雄氏が選んだ児童向けと言われている本を選んだもの、児童だけではなく大人にこそ読んで貰いたい有名な物が紹介されてるけど意外に知らないのもあったし、子供の頃読んでたのに、覚えてないものもあった。長靴下のピッピの解説では、自由なピッピは強烈な逆転の思想を持ち既成の秩序を絶対的と思ってる人に強いパンチを見舞うとある。そうだったのか、ピッピ(笑)映画にもなったマーニーも原作読んでみよう。2015/05/04
フム
9
心理療法家河合隼雄さんの目を通して子どもの本を読むとこんなにも豊かな世界が広がるのかと感心する。それは河合さんが心理療法をする時と同じで、ひたすら相手の主観の世界を共有しようと試みることである。そうすることで、大人が見えない世界、常識にとらわれていては見えない世界に気がつく。作品には大人が眉をひそめるような子どもたちも登場する。『ヒルベルという子がいた』『長くつ下のピッピ』『思い出のマーニー』子どもたちの起こす問題も河合さんの言葉で語られると、意味のあることなのだと納得してとらえられるのがおもしろい2017/08/05