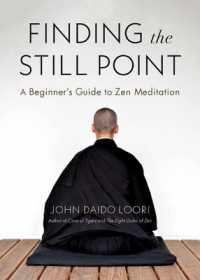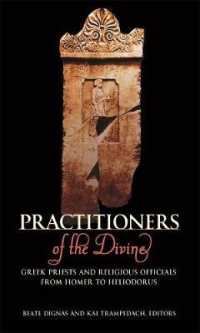内容説明
不登校や拒食症になったり、暴力をふるってしまったり、子どもたちは居場所を失ってさまざまに苦しんでいる。家庭で十分に子どもとしての体験ができないまま育った親のもとでは、子どもは理解されることなく心に深い傷を負う。「ワーク」を通じて、アダルト・チルドレンの心とからだの癒しに挑む著者が、家庭と学校の変革を強く訴える。
目次
1 本当の親・大人とは何かが問われはじめた
2 子どもが子どもとして生きられない
3 居場所のない子どもたち(アル中の父に息をひそめて暮らしたミヨコ;仕事中毒の母に無視されたケイコ;おばあちゃんを慰めつづけるヤヨイ;対人恐怖症のユリ;父親依存症のルミ ほか)
4 教師のからだ―教師たちもいい子で生きてきた
5 家庭を変え、学校を変える
著者等紹介
鳥山敏子[トリヤマトシコ]
1941年生。小学校教師として、からだの視点から授業づくりをするすぐれた実践者として知られた。1994年に教職を辞して「賢治の学校」を主宰。全国を駆けめぐり、「ワーク」と称するセミナー活動を通して、親や子、教師のからだと心の癒しに取り組んできた。それらを通して出会った人たちと、2001年に「賢治の学校」を子どもたちの学びの学校、シュタイナー教育のカリキュラムを実践する学校としてスタートさせた。現在、担任として日々子どもたちの前に立っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
31
不登校やひきこもりなど、子どもたちが今の学校教育にたいしてSOSを出しています。それを子どもたちの「問題行動」として終わらせてはいけません。背景に何があるのか、しっかりと見なくてはなりません。著者は学校や教師に責任を求めることに疑問を投げかけ、今の親子関係の歪み(アダルトチルドレン)に焦点をあてます。個人的にはそのことによってより視野が狭くなっていると感じました。今の子どもや親たちが置かれている現状をもっと深く探る必要があるでしょう。またシュタイナー教育思想が背景にあり全体がすすめられていました。2019/01/14
ステビア
6
はいはいワロスワロス めくっただけでほとんど読んでない2014/03/02
しゅー
3
主観が強かったなぁ。ワークで解決すればいいね。でも自分と向き合うのは大事だよね2021/01/23
しば
3
ほぼ流し読みだったけれど。一種の宗教みたいだった。特に終わり方。ワーク?そんなので泣いて解決するならカウンセラー不必要では?安易な気持ちで、苦しかった過去を再現するのは、良くないのでは。それで治るならその程度か。 求めていたようなACについての本ではなかった。ら2014/05/27
巽
1
全体的に非常に主観的で胡散臭く宗教がかってるという印象が強いが、親にも色々あったんだろうな、ということと、私がこうなのは親のこういう振る舞いのせいかな?という点に思いが馳せれたのは収穫だった。でもそれも私の今のコンディションがあってのことだろうな…タイミングって難しい。現代はもっと、なのか今までとは違った方向に、なのか、私には分からないが、事態は複雑化しているだろうし、大人はもっと子どもになっただろう。この方法論は、もし作中にある通りだとしたらけっこう危険だと思うんだが、今もこの通りなのだろうか。2017/02/04
-
- 洋書
- The Kingdom